「存在のない子供たち」(2018)
- 監督:ナディーン・ラバキー
- 脚本:ナディーン・ラバキー
- 製作:ミヒェル・メルクト
- 音楽:ハリド・モウザナー
- 撮影:クリストファー・アウン
- 編集:コンスタンティン・ボック、ロール・ガルデット
- 出演:ゼン・アル・ラファ、ヨルダノス・シフェラウ、ボルワティフ・トレジャー・バンコレ、ナディーン・ラバキー 他

レバノン出身のナディーン・ラバキー監督による中東の貧困窟を舞台にそこに生きる少年を描く作品。
原題となっている「カペナウム」”Capernaum”は「カオス、混沌」と言った意味でありまた聖書に登場する崩壊した街でもあるそうです。
今作はカンヌ国際映画祭にて審査員賞、エキュメニカル審査員賞を受賞。またアカデミー賞には外国語映画賞部門でノミネートしました。
描かれる人物と現実でも似た境遇にある、演技経験のない素人を配しています。
作品の評価が高く、日本公開も決まってはいるのですが、輸入版ブルーレイが安かったので先に観賞しました。

ゼインは出生証明がないため正確な年齢も分からない少年。
彼は傷害の罪で服役しているが、ある訴えを起こし再び法廷に立つこととになった。
彼が訴えたのは実の両親であり、罪は”自分を生んだこと”。
ゼインがなぜ障害事件を起こしたのか、そして自分を生んだ罪で両親を訴えたのはなぜか。
参考人の証言と共に彼の過去が明らかにされていく。

この作品は社会問題を提起する作品です。ゼインを通して、貧困層の現実を主観的な位置から観客に見せていく映画。
その問題を真正面から見せていく意味でも、もちろん成功していると思いますが、それはゼインの生活、生に観客を引き込む力が強いからだと思います。
映画においてのマジックとは、それが役者による演技であることや演出・設計された映像であることを忘れてしまう没入感だと考えています。
その感覚が見事に構築されています。
役者も実生活として演じる人物に近い境遇に置かれているということが自然さを強くしていると思いますが、ネオレアリズモといっていい写実的で容赦のない描写が続きます。

演技だとしても残酷すぎる、少年の生きる道と彼が守ろうとするヨナスの姿に胸が痛みます。
路上を素足で歩き、水と砂糖を舐めている幼い子どもをみて痛みを感じないことはありません。
映画なのかドキュメンタリーなのか分からないレベルです。そしてこれが現実でも起きているということがさらに悲しい。
カメラは常にゼインの目線の高さに止められ、フィジカルでかなわない年上の青年や大人たちを見上げます。
親に叩かれても反撃できず、大人の男性には立ち向かうことすら難しい。
悔しい思いしかしません。
その悔しい思いは他でもなく私たち大人側が植え付けているという事実も非常に悲しいことでした。

ラバキー監督はゼインたち子どもの側に寄り添い続け、共感と実体験を持って訴えます。
社会的な弱者であることと、人間としても(子どもであるがゆえに)弱い立場にいることを観客に落とし込んで離さない力強さ。
ゼインが一度守れなかった妹に重ねるように、ヨナスを世話する姿。
また冒頭の混沌とした家庭の中で、紐で繋がれた幼児を映しておき、それをゼインが繰り返しながら、親と違って解放してあげるシーン。
弱者が弱者に寄り添う。暖かくも間違った関係です。本当に寄り添うべき人間の欠如。
私が一番、監督が今作を距離をもって(他人事、助ける側)ではなくゼインと並んで描いていると感じたのは、都市部でのお店のシーンでした。
男性がゼインに食べ物を買ってあげようとするのですがゼインは断ります。ここに尊厳を見せているのが素晴らしい。
ただかわいそうで救うべき対象ではなく、一人の人間として施しを受けないという尊厳を持たせること。
これによって、子どもを守るだとか保護するという安易な外側の目線を廃しています。
そして何よりも、彼らを一人の人間として扱うことの重要性を示しているのです。

法廷劇は最小限にして、回想を入れてドラマ仕立てにしているので、サスペンスとかではないですが、法廷に集められることで、隔絶されていた人物が集まり背景が如実に明かされていくのは巧いと思います。
ゼインら子どもも、生まれた証明がなくても、生を受けた時点で一人の人間であり、生きている。
成長するまでは、子どものうちは所有物のような考えは他人事とは思えないところ。
ただ、ナディーン監督は一方的に大人を批判しているようには思えません。
むしろこの環境の外にいる存在こそ、法廷で裁かれている。
両親、またゼインの妹を妻にとった男を責めるのは簡単ですが、彼らの主張が明かすのはもっと根深い問題です。
そうした危険な習慣やどうしても抜け出せない貧困。ゼインの弁護人であり両親を責める役は監督自らが務めていますが、母の答えが印象に残ります。
「あんたに何が分かる。こんな生活の経験もなく、これからもこうなることのないあんたに。」

ナディーン監督はこの作品で、リアリズムを持って貧困層の街をあるく少年の日々を体感させます。それは彼の周囲の人間を責め立てるものには思えません。
こうした現状を知らず想像もできず、まさに存在を認めてもない私たちに向けられた作品です。ショーン・ベイカー監督の「フロリダ・プロジェクト」のように見られていない、いないように扱われている子どもたちにライトをあてている。
本当に見ていて、演技でありこれはクルーがいて撮影しているんだとはわかっていても、苦しい作品です。でも目をそらさずにいるべきだと感じました。
感想としてはこのくらいになります。日本では夏に公開なのでぜひ映画館で見てほしい一本でした。最後まで読んでいただいてありがとうございました。
それではまた。


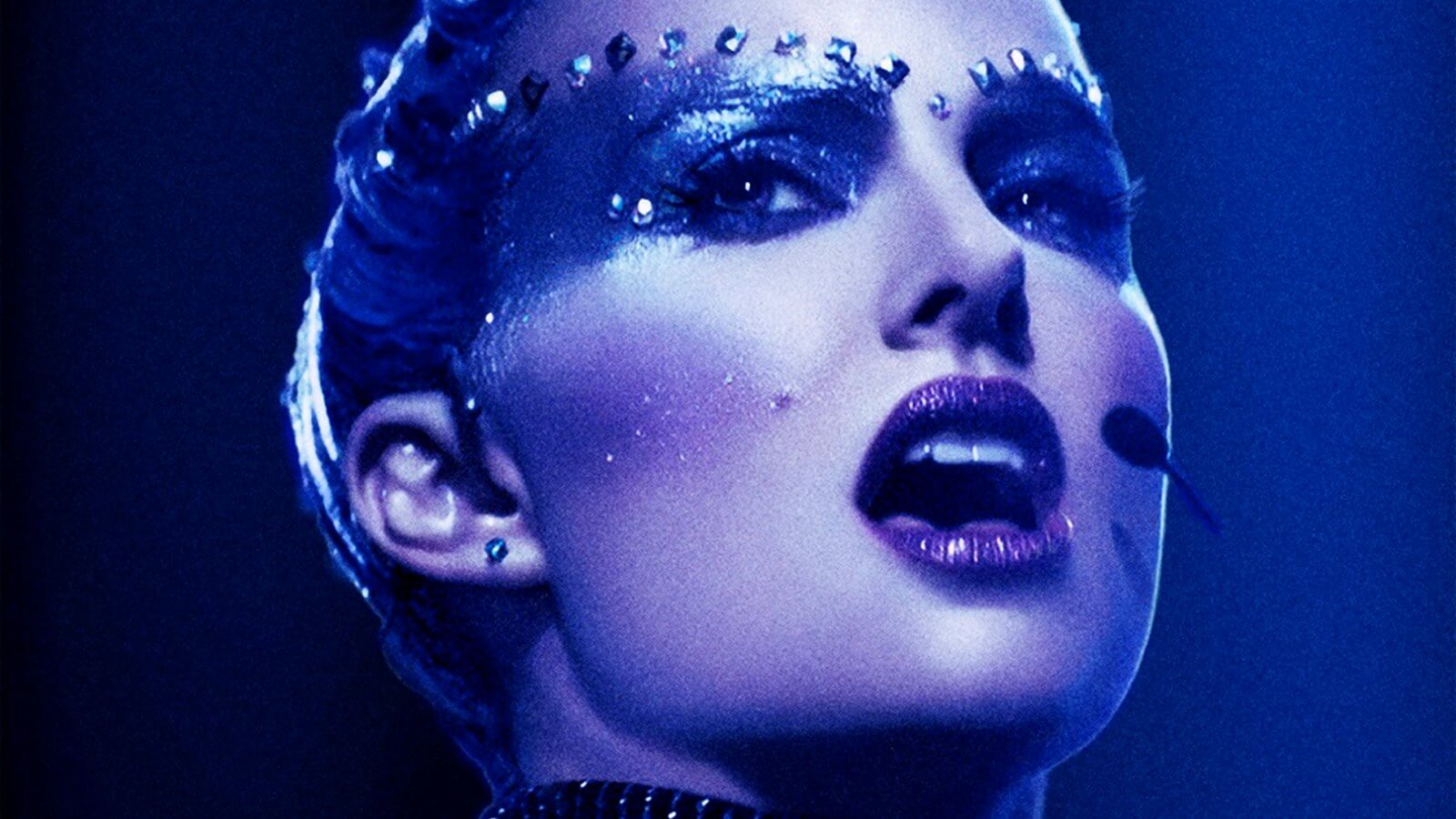

コメント