「最後の決闘裁判」(2021)
- 監督:リドリー・スコット
- 脚本: ベン・アフレック、マット・デイモン、ニコール・ホロフセナー
- 原作:エリック・ジェイガー『決闘裁判 世界を変えた法廷スキャンダル』
- 製作:ジェニファー・フォックス、リドリー・スコット、ケヴィン・J・ウォルシュ、ニコール・ホロフセナー
- 音楽:ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ
- 撮影:ダリウス・ウォルスキー
- 編集:クレア・シンプソン
- 出演:ジョディ・カマー、マット・デイモン、アダム・ドライバー、ベン・アフレック、マートン・チョーカシュ 他
作品概要
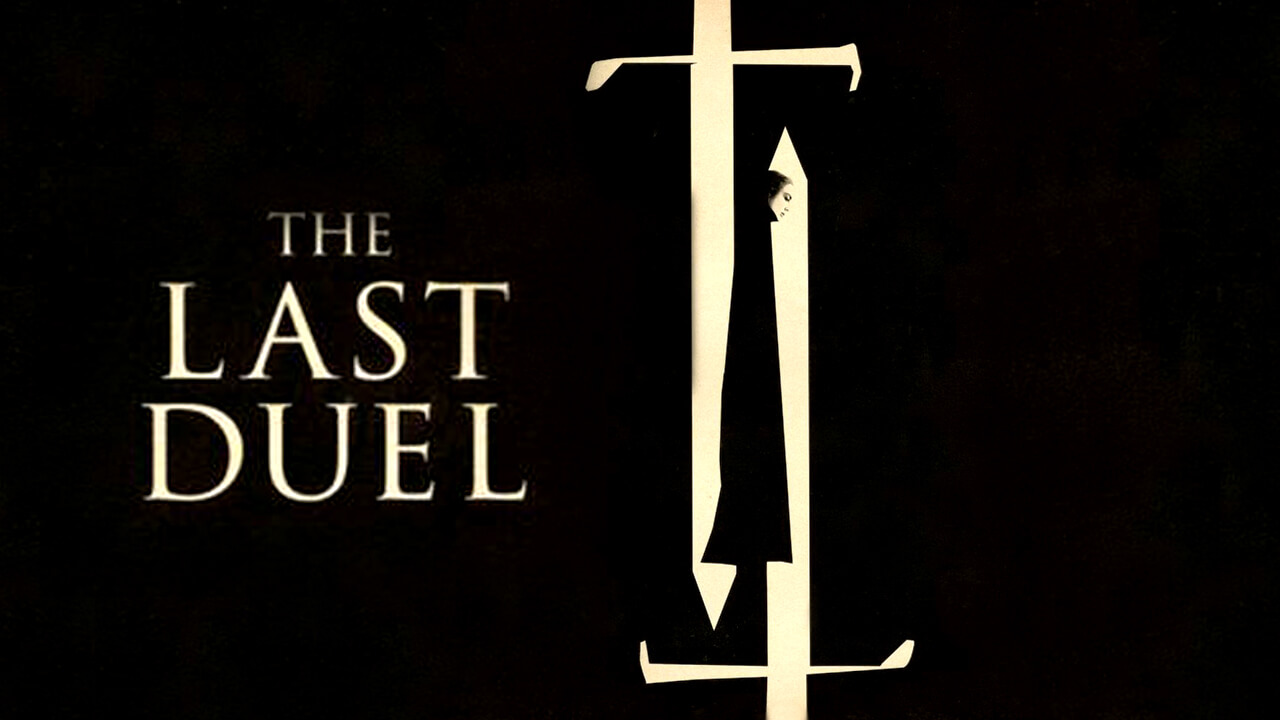
「エイリアン:コヴェナント」から「ゲティ家の身代金」などのリドリー・スコット監督が、14世紀末のフランスにおいて、法で認められ行われたある決闘とその背景を描く歴史ドラマ。
主演は3人の男女となり、騎士の役では「オデッセイ」でも監督と組んでいるマット・デイモン、そして監督の次回作である「ハウス・オブ・グッチ」にも出るアダム・ドライバーが親友であり決闘相手として、そしてこの事件のカギとなるレディを「フリー・ガイ」で素晴らしい演技を見せたジョディ・カマーが演じています。
また、マット・デイモンとは旧友であるベン・アフレックが領主であるピエール伯の役で出ていますが、デイモンとともに脚本も執筆しています。
おおもとの話自体は史実をもとにしていますが、原作としてはエリック・ジェイガーによるノン・フィクション小説である『決闘裁判 世界を変えた法廷スキャンダル』になります。
それをまた映画向けに脚色したということになりますね。
一時は製作がコロナ感染症の影響によって止まってしまったこともありましたが、無事に完成。
早速映画館に行ってきたのですが、公開週末にしては人少なかったです。リドリー・スコット新作ですのにね。なんか年齢層高めの方しかいなかったので、ほかの作品に流れているのでしょうか。
予告
~あらすじ~

14世紀末のフランス。フランス国王の承諾の元、訴えたものと訴えられたものそれぞれが命を懸ける決闘裁判が開かれる。
騎士であるジャン・ド・カルージュは親友でもあるジャック・ル・グリを重罪犯として起訴し、法廷を越え神の名のもとに審判を下すこの決闘裁判を国王に求めたのだ。
国王への直訴は、ル・グリがジャンの妻であるレディ・マルグリットを強姦したというもの。それに対してル・グリは身の潔白を主張している。
事の始まりはこの二人がともに戦場をかけていたころから、そののちル・グリは領主ピエール伯に気に入られたことや、財政難からジャンがマルグリットを詰めに迎え入れたことまでにさかのぼる。
そしてこの二人に生まれた確執と、マルグリットへの暴行事件。
名誉や互いの力をかけ決闘へと進む二人であるが、マルグリットから見えるのはまた別の世界であった・・・
感想/レビュー

今描かれるべき物語
基本的にリドリー・スコット監督はフェミニスト的な側面を持っていると思います。
そもそも「エイリアン」のコンセプトからしても、大きなナニが襲い掛かってくるとか、無理やりに卵を産み付けられる(妊娠)とか、主人公が女性だったりとしますし、やはり彼の中には根源的にそうしたフェミニズムの要素はあると思っています。
そのうえで、この作品は非常に善き狙いと目的を持っていて、また今現代の社会において再び語るべき話であるということは確実です。
そこでこの騎士の決闘、そしてレディ・マルグリットの声を再び現代に呼びよせスクリーンに映すうえで、リドリー・スコット監督は、主となる登場人物それぞれの視点から同じ事件について語るという、黒澤明監督の「羅生門」のスタイルを用いています。
それぞれの視点で描かれルパートはそれぞれ、ベン・アフレックとマット・デイモンが執筆し、最後のレディ・マルグリットの視点にはニコール・ホロセフナー。
彼女は「ある女流作家の罪と罰」などを手掛けており、今作における男性主権社会のフランスに、女性視点を導入するのには最適だったということでしょうか。
しかし、これは仕方のないことでしょうが、その羅生門手法を用いたために同じ話を3回見せていくことになり、ある程度外せなかった部分があるということから上映時間はなんと152分(2時間32分)とかなりの長尺映画になっています。
長尺を覚悟してまで使用したこの羅生門手法ですが、確かにそこかしこにおける語り手による認知や認識の歪み、差異というものを映画的に、画で見せていきその心情や見える世界を届けていくのはおもしろかったとおもいます。
ただし、この題材を描く上で非常に効果的であったかというとやや疑問が残るというのが正直な感想です。

使用した手法の利点と機能不全
まず、この手法であったとして、描きたいのは女性から見た当時の世界やレイプという題材であることは間違いないとおもいます。
だからこそ、ジャン、ル・グレそれぞれの視点での事件と、最後に真実として語られるマルグリットの視点が比較されるのは大切です。
しかし、ジャンとル・グレが結局はマルグリットをめぐって戦っているのではなく、結局は彼女の身に起きたおぞましい事件をネタに、相手を殺すための口実を得て利用しているという点は、もう少し省いても描けると思います。
特に最後のマルグリットの視点では大いにその点を感じ取れますから、あえて細やかな土地の件とか砦の就任の件とか描かなくてもいいのかと思ってしまいます。
女性の視点の映画であれば、もっと騎士二人側は削っていい。
まあ描くほどに愚かさが感じられる点とかはメリットかもしれません。
仲直りの握手シーンでどっちが両手を使うのかとか、命を助けられたことよりも助けたことの方ばかり恩着せがましく覚えていることとか。
とにかく男は自分を良く見せようと語ってばかりです。
あとは決定的に外してはいけないシーンとしてある、レイプのシーンです。
これは映画における主題になっているので避けては通れないわけですが、ここも個人的には諸刃の剣に思えます。
“We couldn’t help each other”「互いに激情に溺れた。」という最低最悪のセリフが含まれているのとか、間接的に脅しをかけて沈黙を促したりする卑劣さを感じられるシーンではあります。
しかし果たしてこの手法によって2度もレイプシーンを描く必要性があったのかは疑問に思います。

と、若干の機能不全というか、主題と手法にかみ合わなさを感じてしまう印象。
描かないと不足するけれど入れ込むと多くなってしまう。3回の別視点語りの弊害はあると思います。
それでも今作は長過ぎて疲れるという点までに至っていないのは、私は主演3人の力であると思いました。
あと最後にはゴア全開で殺し合いする「グラディエーター」を思い出すバトルもあって吹き飛ぶということもありますが。
まあ演者に関してはもともとベン・アフレックがグ・グレをやるところ、ほかの作品とのスケジューリングもあってアダム・ドライバーが来たらしく、やはりアダム・ドライバーすごいなあというところ。
顔立ちからしてもなんか14世紀フランスの人っぽいのもあるんですが、口からいろ色言っていても結局女を性のはけ口にしか思っていないこと、そのくせ「愛している」だの言っちゃう薄気味悪さなど、絶妙です。
そして誇らしく思えるくらい素晴らしいのがジョディ・カマー。
変幻自在だった「フリー・ガイ」で魅了された人も多いと思いますが、マルグリットの娘、妻、母そして女性としての様々な苦悩や当時の女性の何者でもなく何も持たないつらさ、孤独を彼女のおかげで感じ取ることができます。
話の中心でありながら、所有物でしかなく男同士の話になっている、しかしやはりこの映画の主人公です。
金と土地がくっついているという理由で父に売られるように結婚させられ、子どもを授かるための道具でしかない。
少し男をほめれば気が合ったのではと言われ、裁判でのセカンドレイプっぷりには苦痛しかないですね。

女性たちの表情、尊厳
代表されるのがマルグリットであるにしても、女性たちの表情が忘れられません。
特に決闘もこの件もすべてが娯楽のようで楽しそうな国王に対して、横にいる王妃のなんとも苦しそうな顔。
何ももっていない。位があろうとも金を持っていても、誰かの妻や母であってそれは結局男の資産。
そんなことはこの14世紀末だけと思いたいですが、同じようなことは確実に現代にも見えています。この時代にマルグリットは声を上げ続けた。
夫のためとか名前のためとかじゃないんですよね。自分自身の存在と尊厳。
「俺に嫌がらせばかりする!」という言葉に対して、被害者、尊厳を傷つけられたのは自分であると主張し決して沈黙しません。
その勇気と声は現代にも響き渡ることになります。
ちなみにこの事件と決闘についてはいろいろとこの後の啓蒙時代においても意見が分かれたりしているようです。一応は真相証明の証拠がないのでなぞということなのでしょうか?まあマルグリットの声そのものを消し去ろうという試みは失敗していますけれど。
各パートの文字の出方と、消え方においてマルグリットの物語であること、彼女の声から女性の尊厳を描く作品であることは間違いありません。
俳優陣も素晴らしいですし、あとはすこしクドめにかんじる語りの手法ですが、決してダレルとか退屈することはないのはさすがリドリー・スコット旦那と思った映画でした。
気になる方はぜひ劇場へ。
今回の感想はこのくらいになります。ではまた。




コメント