作品解説

「スペンサー ダイアナの決意」でアカデミー賞候補となったクリステン・スチュワートと、「ミッション:インポッシブル/デッドレコニング」に出演した元ボディビルダー俳優ケイティ・オブライアンが共演するクィア・ロマンス・スリラー。
物語とキャラクター
- ルー(クリステン・スチュワート)
父親を嫌悪しながらも、その影響下から抜け出せない複雑な女性。 - ジャッキー(ケイティ・オブライアン)
ルーの恋人となるボディビルダー。彼女の人生を大きく変える存在。 - ルーの父(エド・ハリス)
圧倒的な力で周囲を支配する存在。ルーに深い影を落とす。 - その他共演者にはジェナ・マローン、アンナ・バリシニコフなど
監督と演出
監督は「セイント・モード 狂信」で注目を集めたローズ・グラス。
ノワール、ラブストーリー、スリラー、さらにはユーモアまで、多様なジャンルを横断しながら、大胆かつ示唆的なストーリーテリングを展開していきます。
公開前から代った設定自体に惹かれていて、しかも好きなクリステン・スチュワートの出演作なので期待をしていました。
実は「セイント・モード」の評価が高いことは知りつつ、観たことがなく、ローズ・グラス監督の作品は初めての鑑賞に。
週末は行けなかったので平日仕事帰りに見てきました。公開規模の小ささもあるのですが、スクリーンは満員に近い状態でした。
~あらすじ~

1989年。トレーニングジムで働くルーは、夢を追ってラスベガスへ旅立とうとする野心的なボディビルダー、ジャッキーと出会い、たちまち恋に落ちる。
しかし、ルーの周囲には暗い影が落ちていた。街の裏社会を牛耳る冷酷な父、暴力的な夫に苦しめられる姉――家族の問題は彼女の心を縛りつける。
そんなルーを守ろうとするジャッキーの思いは、やがて彼女自身を予期せぬ犯罪の渦へと引きずり込んでいく。
感想レビュー/考察

「Love Lies Bleeding」のタイトルが示す意味
タイトルはLove lies bleeding。ヒモゲイトウ((アマランサス))の英名でもあります。その花言葉は「終わりのない愛」「不滅」「粘り強い精神」など。
英語としてのLove lies bleedingを直訳すると「愛は血を流して横たわる」という意味。でも今作では愛は血を流す。愛は痛みを伴う。といった意味合いが最適なんだと思います。
今作は非常に不思議な映画です。複合的なジャンルを持っている。でも私はまとめ上げればこれはラブストーリーであり、その本質をノワールで包んでいるからこそ、この愛は血を流すというタイトルがピッタリだと感じました。
不穏なノワール感に包まれるオープニング
不可思議なラブストーリーですが、根底のノワール感がOPから始まっています。
不穏な音楽の中で、奥底の見えない地獄へ開いた口のような岩場をのぞき込む。真っ赤なライティングがとにかく不穏な中、築けば星空が見え、そしてカメラがパンしていくと主人公ルーが働いている砂漠のジムが見えてきます。
ジムのオーナー・ルーの登場と「行き詰まり」の象徴
ルーはこのジムのオーナーということですが、彼女の初登場時はその威厳は感じられない。詰まったトイレに手を突っ込んで掃除しているのです。
今作でまれにみる純真な(そして可哀そうな)キャラであるデイジー(演じているのはアンナ・バリシニコフ)が、ルーを遊びに誘うのも、ルーはさらりと断っていく。
ルーはクソダメに詰まっている。そんな要素が示される中で、今度はスクリーンにジャッキーが登場します。

居場所を持たないボディビルダー・ジャッキーの強烈な初登場
しかし、ジャッキーの初登場はまさかのカーセックス。彼女に後ろから覆いかぶさるのは妙な髭を生やしておかしなデイヴ・フランコ演じるJJ。ジャッキーはヒッチハイクを繰り返し、拠り所を持たないで生きる女性。
橋の下で目を覚まし、その辺の策を使って懸垂して体を鍛える、ボディビル選手権での優勝を目指す女性。ルーと反対に居場所を持たないものの、やはり社会システムの中では弱者に分類されます。
でも、ルーにとってはジャッキーの姿勢が衝撃。それは二人が仲良く話しているとき言い寄ってきた男に、迷わずパンチを打ち込むこと。しわ寄せ食らいがちなルーにとって、フィジカルに殴り返すジャッキーは衝撃です。
ルーとジャッキーの出会いが生む“愛と暴力”の物語
今作はそんな二人が出会うことで大きな展開をしていく。行き詰まりどこかへ逃げたいルーと今いるべき場所を持たず目標だけ持っているジャッキーの二人が、素敵な恋に落ちていく。
クリステン・スチュワートとケイティ・オブライアンのケミストリーも結構いいものですし、直接的な性描写がありつつ、二人のエモーションを先行しながらもどこかファンタジーにも見える。
そんな二人がやっとお互いを見つけたような、そんな奇跡も、ローズ・グラス監督はノワールスリラーの響きを高めていくことでジャンルをシフトし、彼女たちを闇へ叩き落していきます。
全てはJJというクソ男がいるせいですが、ルーは大切にしている姉ベスとその夫のJJ、そしてジャッキーの4人で食事に行く。
そこでのJJのベスに対する態度、怒りをあらわにするが抵抗はできないルー。それを眺めていたジャッキーは、こらえられない力を増していくのです。

衝撃のボディホラー的変身シーン
決定的なDVでベスが病院送りにされたことで、ボディホラーのように(まるでインクレディブル・ハルク)ジャッキーは変身をする。それが現実に起きているようなことなのかメタファーなのかは定かではないですが、天井にも届くほどの大きさに変貌したジャッキーはJJを叩きのめします。
JJがどんな姿になったのかが、彼女を探しに来たルーの視点でみせられますが、顔のほとんどが潰れ千切れ飛んでいるという強烈なビジュアルが、バイオレンス映画としての爆発をみせました。
血まみれのノワールを彩る“父の影”とルーの絶望
そこからはまさにノワール。行き詰まりの若いカップルがあの手この手で犯罪から逃げようとする。
そこで強烈な印象を残す、エド・ハリス演じるルーの父親。ヒッピーの悪魔みたいな?見た目しているとにかく不気味で怖い造形のエド・ハリス。
背景が最終的に描かれますが、どうやらこいつは地元警察すら牛耳るギャングのボスであり、そしてルーは昔父のために処刑人をやらされ人を殺したことがあるのですね。
その世界から逃げ出したくて離れているけれど、結局は父の保有するジムのオーナーをあてがわれているというのは滑稽でありそして絶望です。
愛と暴力が交錯するクィア・ロマンス
二人の愛には血みどろのドラマがある。お互いを愛するあまり、くやしさや嫉妬もある。ちゃんとラブロマンスしていて、しかしスラッシャーレベルのノワールである。
そこにはクィアな関係性もあるけれど、最後の最後には超絶なジャンルジャンプを繰り出すことに。巨大な女性というものがスクリーンに出るのって、もはやあまり見たことはないですが、巨人女はちょっとセクシーな雰囲気を持っている。
でも、今作のジャッキーは違う。愛の大きさそのもののように強大で、そしてこれまでと違う形で、フィジカルに男性を越えてパワーであいてを圧倒し黙らせていくのです。
それはあのJJのように、暴力で女性を黙らせてきた男性ばかりが描かれてきた中で、その存在自体が重要にも思えました。
爽快なクライマックスの中で、ジャッキーのおかげでルーも大きくなれたのでしょう。でも最後の最後に苦い詩を横たえるのも、またノワールらしい終わり方でよかったです。
ローズ・グラス監督が描き出す愛の物語は尋常ではないけれど純愛で、クィアネスもフェミニズムもぶち込んで様々な顔をのぞかせる。散らからないのは、まさに、芯がしっかりしていて描きたいことがはっきりとしているからなんですね。
とてもおもしろい作品でした。今回の感想はここまで。ではまた。

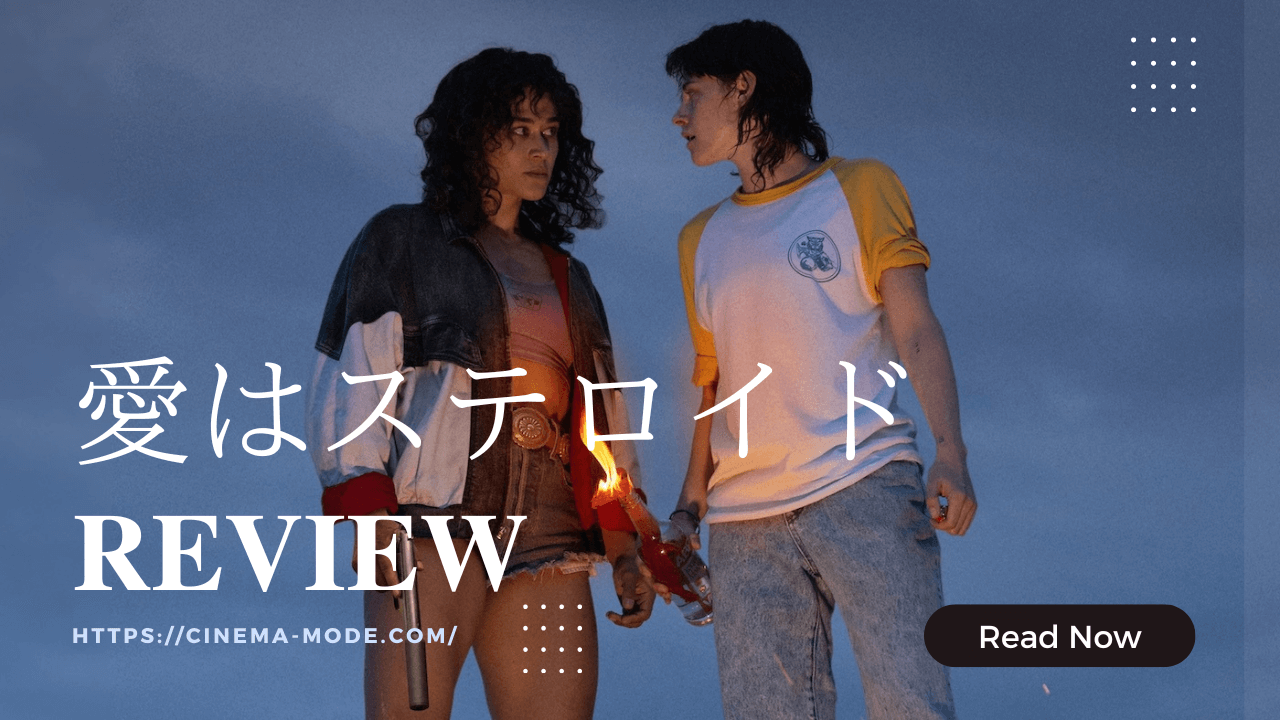


コメント