作品概要

ギレルモ・デル・トロが描く新たなゴシックホラー
19世紀イギリスの作家メアリー・シェリーによる古典的ゴシック小説「フランケンシュタイン」を、ギレルモ・デル・トロが映画化。
「シェイプ・オブ・ウォーター」、「パンズ・ラビリンス」で知られるデル・トロが長年映像化を熱望してきた企画で、製作・脚本も自ら担当。
物語は、科学への飽くなき渇望に取り憑かれた若き研究者ヴィクター・フランケンシュタインが、新たな生命の創造に挑むところから始まります。
やがて誕生した「怪物」の存在は、人間とは何か、そして真のモンスターとは誰なのかという普遍的な問いを投げかけていきます。
キャスト情報
- ヴィクター・フランケンシュタイン:オスカー・アイザック
「スター・ウォーズ」シリーズ、「DUNE デューン 砂の惑星」などで知られる実力派俳優。 - 怪物(クリーチャー):ジェイコブ・エルロディ
「プリシラ」、「Saltburn」で人気急上昇中の俳優。 - その他キャスト
ミア・ゴス(「X エックス」)、クリストフ・ヴァルツ(「ジャンゴ 繋がれざる者」「イングロリアス・バスターズ」)、フェリックス・カメラー(「西部戦線異状なし」)など
映画際出品と公開情報
本作は、2025年の第82回ベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品され、10月24日には一部劇場で先行公開されました。
その後、11月7日よりNetflixで世界配信が開始されています。
渋谷とかで限定公開されていたのですけど、仕事も忙しいし東京国際映画祭も始まったりで全然いける気配もなく、結局ネトフリの配信開始とともに鑑賞しました。
~あらすじ~

1857年、北極探検の途中だったデンマーク海軍の探検船ホリソント号は、厚い流氷に閉じ込められてしまう。
乗組員たちは、付近で発見した、重傷を負ったヴィクター・フランケンシュタイン男爵を救護していたが、突如として“怪物”が現れ、ヴィクターの身柄を引き渡すよう要求する。
危機に直面した船長アンダーソンに、ヴィクターはついに真実を告白する。
──自分こそが、怪物を創造した張本人である、と。
そして彼は、禁断の実験に手を染め、怪物が誕生するまでの経緯を語り始めるのだった。
感想レビュー/考察

フランケンシュタインとは誰のことか
このフランケンシュタインについて、ちゃんと整理がつかない人もいまだ多いので改めてですが、フランケンシュタインはあの人間の博士のことです。
よくハロウィンとか怪物図鑑に出てくる四角い頭で首にボルトが刺さってて、皮膚に縫い目がある大男は”怪物”。名前も与えられなかった”フランケンシュタインの怪物”です。
さて、そんな基本的な整理をした後で今作について考えてみます。
デル・トロ監督が描く「異形」と「魂」
デルトロ監督といえば異形、モンスターを愛しながらも、そこに美しい魂を見ること。
「シェイプ・オブ・ウォーター」がとくに有名ですけれど、姿かたちと精神の対比ではこのメアリー・シェリーの物語は監督にピッタリな題材だと思います。
デルトロ監督は原作をなぞりながらも改変を加えていて、特に今作のラストについては非常に希望ある帰結の仕方にしています。
多くの場合には悲しい物語になるこのフランケンシュタインとその怪物の話なんですよね。
でも、この作品は確かに非常に切ないものがありながらも、赦しと解放をもって、死をつかさどってきた物語に、生きることの素晴らしさを与えていました。
その意味では革新的であり監督らしい作品に仕上がっていると思いますし、怪物の物語の切なさの中から人間の本質的な孤独や、生きることということのあまりの残酷さはこれまでも語られていたように持っている。
でもそこにこんなにも暖かなラストを携えたことは宝物のような作品だったと感じます。

美術面で際立つ作品の魅力
作品の各セクションに関して、さすがに美術面での楽しさは格別でした。
デルトロ監督の世界観。
「ナイトメア・アリー」などでもデルトロ監督と組んでいるタマラ・デヴェレルがプロダクションデザインの担当で、時代劇としてのルックはもちろんのこと、全体を覆う絵画的な光と闇など見た目にも楽しい。
不気味でありながらも美しさを感じるような造形の数々。
宗教性・神話性を帯びた造形の数々
今作は宗教的な、創造主と人間、博士と怪物という神との対話のような要素もあり、どことなく神話の世界のような造形物もあって好みでした。
実際、博士の研究室にあり、怪物も眺めることになるのは大きなメデューサの顔の像です。
メデューサもまた、神々の呪いによって怪物に帰られた悲しい宿命を負った怪物ですし、テーマとしてもあったモチーフになっています。
ちなみに監督のこだわりで、フランケンシュタイン博士や怪物が語りをすることになる船内とか、博士の研究室などは全部実際に作り上げたセットだそうです。
リアルさを追うところ、モノに魂を宿すところのこだわりは、この映画の”モノに命を吹き込む構造”にも重なります。
ローストセン撮影監督による統一された映像美
撮影に関しても「シェイプ・オブ・ウォーター」や「ジョン・ウィック:コンセクエンス」などのダン・ローストセンが撮影監督として見事な仕事をしています。
舞台が意外に多くて、氷上に森林、屋敷内や研究室に地下室などいろいろな場面が出てきますが、全体に統一され柔らかな色調や艶やかさが素敵でした。

エリザベスに象徴されるグリーンの色彩
色彩でいうと今回怪物にとって初めての理解者であり、今作の中でも印象深い、ミア・ゴスが演じるエリザベスのカラーがグリーン。
グリーンの美しいドレスが印象的な彼女に重なり、怪物も森の中という緑の中で鹿に触れあい癒しを得ます。
フランケンシュタイン博士の異端性が際立つ人物造形
衣装回りの人物造形でいうと、異端児であり先駆者的なフランケンシュタイン博士、彼の衣装とかヘアメイクなんかも結構尖ってた。
オスカー・アイザックにはいかにも研究者的なルックを与えずに、むしろアナーキストみたいな崩した様相を与えています。
この二人の演技の良さもありつつ、彫り込まれたドラマも巧妙です。
エリザベスとの関係に重なる母性の影
ヴィクターは幼いころからチャールズ・ダンス演じる父親に虐待的な教育を受け、資質も存在価値もすべてを否定されてきた。それを包容してくれていたのが母親でした。
今回はその母もミア・ゴスが演じていますが、彼女の死によってヴィクターは自分の存在を承認してくれた存在を失う。
だからこそ自分自身が活きていることを叫び続けるように研究に没頭し、そして母を奪った父を激しく憎んだ。
彼の母への思いは同じくミア・ゴスが演じたエリザベスに惹かれるところでも見えますが、小道具の使い方が結構おもしろい。ヴィクターはかなりの頻度で牛乳を飲んでいるんですよね。
そこにはなんとなく、母性への渇望とかを忍ばせていると考えざるを得ませんでした。

父と子の関係性が繰り返される構造
その様子を見れば、同じ構造が繰り返されているということになります。
期待しつつ誕生させたものの、結果に満足できず忌み嫌う父。ヴィクターと父親もそうですが、怪物とヴィクターの関係も一緒です。
そして、その怪物に寄り添い理解しようと優しくしたのもエリザベスです。
自分が受けたような身体的虐待を怪物に対して繰り返したヴィクター。しかし、怪物は知性を高めその創造主である父を越えていく。
自分を超えることへのコンプレックスも含めてヴィクターはさらに怪物を恐れて嫌うことになる。
中核にはこの二人の父と子の物語があり、なんとも神話的です。
人間という存在の本性
しかし、ほかにも怪物が純粋な存在として様々な人間と触れ合っていくことから、人間という存在の本性や逃れられない性質にも向き合っていくことになります。
戦争が背景にあり、大量の骸がさらされる時代。死刑執行のための列には多くの罪人が並び、次々につるされていくこの世界には、赦しなどない。
弱者を強者が食い殺す世界。人は暴力にまとわりつかれている。
そんな世界で死を乗り越えてみせんとしたフランケンシュタイン。死者をよみがえらせ生を与え、神のごとく振舞おうとした。
劇中でオジマンディアスの詩が引用されます。(この詩の作者はパーシー・ビッシュ・シェリー、「フランケンシュタイン」原作者メアリー・シェリーの夫)
それは王の中の王を語った独裁者の、その哀れで寂しい残骸を観たものの言葉です。

怪物の孤独と赦しが交差する、物語の最終章へ
怪物は残酷な世界を知り、それでも生の温かさにも触れ。死ねないという呪いを解決するため、それはつまり残酷すぎるこの生をどのように終わらせられるかを考えた。
生きていてもつらいだけなのだ。だからこんな世界に産み落としたヴィクターに怒り、伴侶を求める。
でもヴィクターは愛想を尽かしている。
二人の物語はそれぞれの視点で語られた最終幕に、ついに交差します。そこにあったのは赦しです。
どちらも、ただ愛されたかった。それなしに生きるにはあまりにも辛いこの世界を生きて行かなくてはいけないなら。せめて愛されたい。
フランケンシュタインの物語に刻まれた、新しい光のチャプター
叶わなかった渇望が暴力となり連鎖する。
だからこそ最後の赦しが最大の癒しとなります。ついに”それ”とか”怪物”ではなく、”息子”と呼んだヴィクター。怪物は優しいキスをして父の眠りを見届ける。
そして、初めてこの世界の朝日を観たときのように、父が「太陽の光、命。この温かさが生だ。」と教えてくれたように、怪物は闇ではなく光を向く。
生きてこそなのだということ。
最後には死ぬために消えて行ったりするこのフランケンシュタインと彼の怪物の物語の新しい語りの中に、こんなにも美しく優しいチャプターを作り上げたデルトロ監督に感服です。
ネトフリ加入されている方はぜひ鑑賞を。おすすめの作品でした。
今回の感想はここまで。ではまた。


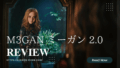
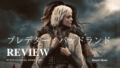
コメント