「アンデッド 愛しき者の不在」(2024)

作品解説
- 監督:テア・ビスタンダル
- 製作:クリスティン・エンブレム、ギュリ・ネビー
- 製作総指揮:スバイニュン・ゴリモ、エミリー・トーマス
- 原作:ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィスト
- 脚本:ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィスト、テア・ビスタンダル
- 撮影:ポール・ウルビック・ロクセット
- 美術:リンダ・ヨンソン
- 音楽:ピーター・レイバーン
- 出演:レナーテ・レインスヴェ、ビョルン・スンクェスト、アンデルシュ・ダニエルセン・リー 他
「ぼくのエリ 200歳の少女」、「ボーダー 二つの世界」の原作者として知られるスウェーデンの作家ヨン・アイヴィデ・リンドクヴィストの2005年の小説を映画化した北欧ホラー。
監督は、ミュージックビデオや短編映画で活躍してきたノルウェーのテア・ビスタンダル。本作が長編デビューです。
脚本は原作者リンドクヴィストとビスタンダル監督が共同で担当。
「わたしは最悪。」のレナーテ・レインスヴェが主人公アナを演じ、「ハロルドが笑う その日まで」のビョルン・スンクェストが父マーラー役。「パーソナル・ショッパー」や「ベルイマン島にて」のアンデルシュ・ダニエルセン・リーも共演しています。
昨年知人から進められて存在を知りつつ、公開は年明けとなった本作。早速公開週末に観てきたのですが、そこまで混んではいなかったです。意外に若い方が来ていました。
~あらすじ~

ノルウェーのオスロ。最愛の息子を亡くし、深い悲しみに沈むアナとその父マーラー。
また別の場所では、最愛のパートナーを失った老婦人がおり、そして別の場所では交通事故で急に妻を失った夫と、子どもたちがいた。
そんなとき、オスロでは大規模な電波障害や電気系統の混乱が発生。
同じとき、墓地でかすかな音を聞いたマーラーは衝動的に孫の遺体を掘り起こし、自宅へと持ち帰る。絶望の中にいたアナは、その存在によって徐々に生気を取り戻し、誰の目にも触れないよう山荘で息子とともに暮らし始めた。
しかし、蘇った息子は瞬きも呼吸もするが、一言も発しない。そして、不穏な気配が漂う中、思いがけない訪問者が山荘を訪れる。
同じ頃、別の家族にも予期せぬ運命が待ち受けていた。
感想レビュー/考察

北欧ホラーの新たなチャプター
北欧ホラー。「ミッドサマー」が大衆に知らしめ、「ハッチング -孵化-」や「イノセンツ」、そして最近はスリリングな「胸騒ぎ」など、独特なテイストを持ったジャンルとしてぐっと注目されている作品カテゴリ。
そこに新たに加わるのが、「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」のような古典的なテーマの作品。何らかの天変地異なのか、神の御業か世界の終末か。死者がよみがえり現世を闊歩する。
そんなクラシックなホラーも、北欧テーマになればゴアグロ血まみれゾンビバトルにはならず、しんみりとしてどんな感情で観ていけばいいのか分からないような作品になっていました。
そう、感情を定められない。これまでは内容に対して画面がとても明るく美しいというギャップがあったり、静かにしかし確実に蝕むような陰湿な怖さがあったりした北欧ホラー。
今作は全体には色彩にかけていて灰色がかって寒そうな画面に、黙々として静かで慎重なストーリーが重ねられる。なのでギャップはない。
超常的な恐怖に、人間らしい愛しさとドラマ
でも、蘇る死者が最愛の人々であるという点で、恐ろしさもあるけれど喪失を抱えた人間ドラマでもある。だから怖いような、それでいて切なく愛しいような。処理しきれない感情を抱えてみていくことになりました。
超常的な現象、人間の理解を超えた存在。それに対してエゴともいえる行動で、しかし実に人間らしい選択をしていく。この点では「LAMB ラム」に通ずるものがあります。
あちらも、我が子を失った悲しみに耐えきれない夫婦が、禁断の子どもを身勝手にも、自分の子どもとして育てていく話です。
この両面性というか恐怖と愛しさが同時に存在する感じ、実に良いですね。

台詞に寄らない語り
その人間らしいドラマですが、テア監督は最愛の人を失った悲しみとそれをどう処理していくのか、その感情を普遍のものとして描き出します。手法が良い。
まず素晴らしかったのはOP。
何やら深刻な面持ちでタバコを吸う老人が、狭い扉の隙間というフレームの奥に映し出されます。
彼は食事を容器に映し、袋に入れて家を後にする。そしてカメラは断続的に回り続け、静寂の中で老人は近くのマンションへ移動します。
動かないエレベーターを諦め重い足取りで階段を上り。部屋には若い女性がいますが、二人はほとんど会話をしない。
そして老人が持ってきた食事を食べずに女性は仕事へ行ってしまう。老人が彼女の分の食事を冷蔵庫へしまうとき、何日ぶんか、同じような食事がそのまま放置されていました。
そして、冷蔵庫には老人と女性、少年が映った美しい写真が貼られている。
この会話によらない映像で語るシークエンスが、今作を象徴すると思います。
表層で起きていることの奥を推し量り感情を人物たちとつなげていくとき、異常事態も恐怖も感じながら、1つの答えの出せない人間の普遍的な悲しみに触れるのです。
全体に会話が少なく、そして3つの家族はそれぞれ子どもから大人パートナーから親まで、誰しもがいずれかの人物に寄り添えるような幅を持っています。
すごくリーチが広くアクセスしやすいと思ったのです。

監督自身もインタビューの中で、このような幅の広さ、セリフを抑えることによる余白の確保について言及しています。
喪失感によりそもそも何かを発現するエネルギーを失っていること、どう表現していいか分からないこと。だからこそ映像で語ることに力を込めたと。
喪失を受け入れること
テア監督は、最後にギアを切り替えます。終末のゾンビ映画として、残酷な場面もでてくる。それが急だと感じる観客もいるでしょう。
ただ、そこまでの静かなパートでも、一定の不穏さを出していましたし、噛むことを強調するシーンもありましたので個人的には気にはならないレベルです。
姿形は愛しい人だけれど、心臓も動いているけれど。死んでいる。
そこに魂がないからです。
最終的に母は息子の死を認めます。土ではなく水の中へ息子を還していく。
夫は妻の死を認め、子どもたちも涙する。いつしか大切な人はなくなってしまうから、別れを言う必要がある。
世紀末のゾンビ映画でありながら、人との別れやそれを受け入れるプロセスを描く作品。
しっかりと不気味で怖い部分もありますし、複雑で難しい感情を持たせる作品です。単純なゾンビ映画でもない独特の味わいがすごく印象的でした。
今回の感想はここまで。ではまた。

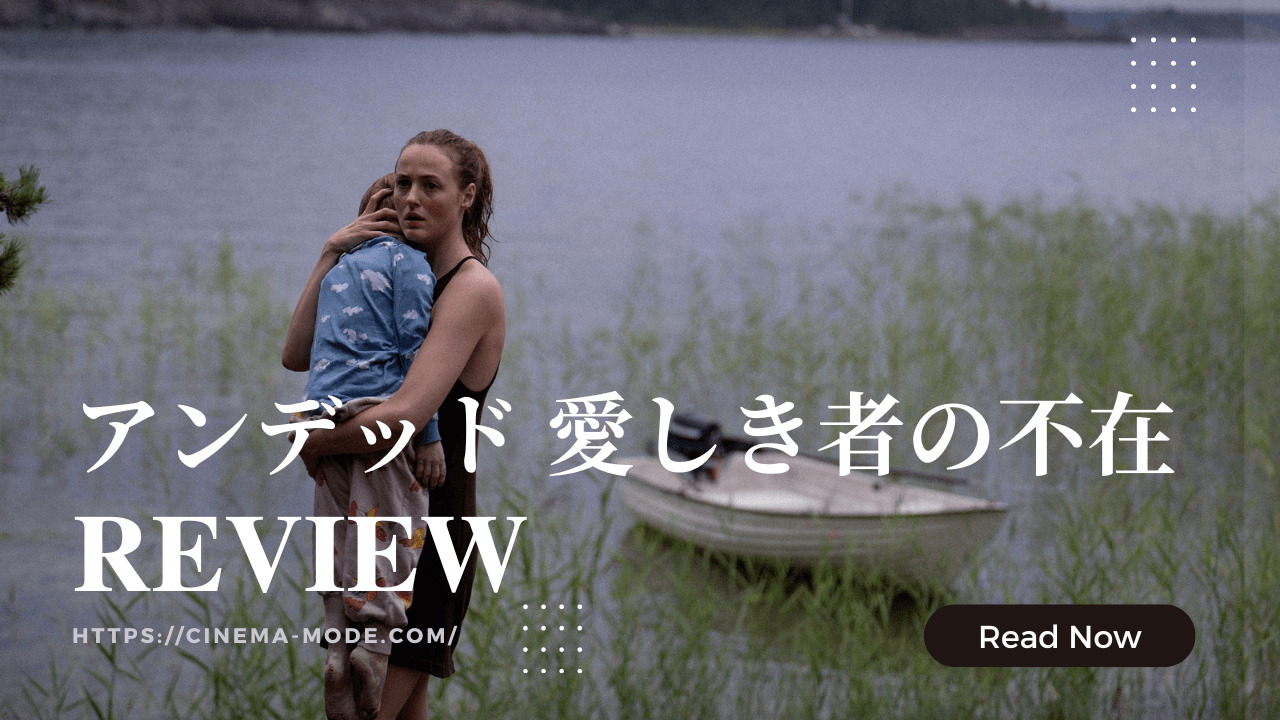


コメント