「グレース・オブ・ゴッド 告発の時」(2018)
- 監督::フランソワ・オゾン
- 脚本:フランソワ・オゾン
- 製作:エリック・アルトメイヤー、ニコラ・アルトメイヤー
- 音楽: エフゲニー&サーシャ・ガルペリン
- 撮影:マニュエル・ダコッセ
- 編集:ロール・ガルデット
- 出演:メルヴィル・プポー、ドゥニ・メノーシェ、スワン・アルロー、エリック・カラヴァカ、ベルナール・ヴェルレー、フランソワ・マルトゥーレ 他

「スイミング・プール」や「危険なプロット」などのフランソワ・オゾン監督が、フランスにおける神父による自動性的虐待の事実、プレナ神父事件を映画化した作品。
被害者として声を上げ始める男性たちの役には、メルヴィル・プポー、ドゥニ・メノーシェ、スワン・アルローら。
作品は公開当時も操作の進む事件を取り上げており、日本公開は2020年となりましたが、今もなおリアルタイムで進展をみせ、被害者たちが戦い続けています。
ベルリン国際映画祭にては銀熊賞を獲得、さらにスワン・アルローはセザール助演男優賞を獲得しています。
割と大きめに報道されていたかは記憶があいまいですが、やはりカトリック教会の聖職者による児童への性的虐待は「スポットライト 世紀のスクープ」もあったように記憶には焼き付いています。
今回は批評の良さもありますが、どことなく、観ておこう知っておこうという気持ちが強く鑑賞した作品です。
朝早い回だったのでそこまで混んではいませんでした。

フランスのリヨン。
アレクサンドル・ゲランは自分の子どもが通う学校で、保護者の一人と自分たちが子どものころに参加していたカトリック教会のサマーキャンプの思い出話をしていた。
すると相手は「君もプレナ神父に触られたの?」と言われる。
それは、アレクサンドルのトラウマである、教会のプレナ神父により繰り返されていた性的虐待であった。
これまで声に出せず、沈黙していた彼は、その会話から他にも多くの犠牲者がいると知り、さらにプレナ神父はリヨンに戻り今でも子どもたちを教えているのだった。
傷口を開くことは耐えがたい苦痛であったが、信者として教会を進化させるため、子どもたちを守るために、アレクサンドルは被害者を探し告発することを決意する。

アプローチに関してはどうしても「スポットライト 世紀のスクープ」と比べてしまうことがありましたが、今作はかなり個人に近寄った話になっていると感じます。
3人の男性に主眼を置き、社会的なムーブメントやカトリック教会という組織と地域など大きなスケールに移行することなく、あくまで3人の個人がこのような児童精神虐待を受けてどんな影響を受けているのかをクローズアップしたつくりです。
距離が近いということもあってか、3人のそれぞれの苦しみや不安、恐怖が体感型のように襲ってくるものになっています。
事件を俯瞰する立場としての映画作品というよりも、共有し痛みを分かつように感じます。
もちろん、その直接的な描写をしないものになっています。ここは個人的には正当化と思います。もしも直接に再現して描写をすれば、もちろん苦しいこともありますが、重要な共感を薄めてしまうと思うからです。
実際に今目の前で起きているわけではなく、また画面に出てくる被害者たちが、自ら語る言葉以外に、この事件を覗くことはできません。
しかし、その声に耳を傾けることは大切です。
スクリーンを通してでも、遠い国で数十年前に起きたことを今語られるというだけの情報から、私たちは痛みを知ることができるはずです。

そしてそれぞれ違った形で痛みとともに生きる3人の被害者を演じるメルヴィル・プポー、ドゥニ・メノーシェ、スワン・アルローもとてもよかったですね。
個人的にドゥニ・メノーシェは「ジュリアン」以来怖い人なんですが、今作では被害者の一人として、ちょっと明るく過剰な感じもあるフランソワを演じていました。
彼らを描くときに、決して被害者とプレナ神父(教会)の二項対立にせず、もちろんそれぞれの人生の形成を描きながら、暴力が広がった先にいる、間接的被害者たちも描いているのは素晴らしいと思います。
人間関係の形成そのもの、両親や家族などの関係と彼ら自身の人生。
フランソワの兄は弟を愛しながらも、彼を中心に流れていった幼少期を失いました。それはまた、直接でなくてもプレナ神父が奪ったものでしょう。
またエマニュエルは身体的にも経済的にも追い込まれています。しかし加えて、彼に起きたことは両親の関係にも影響したのです。
またアレクサンドルの子どもたちも印象に残ります。父がそのような被害者であることを知ること。過去のことだなんて言えません。
誰の人生と切り取っても、被害者はその人だけではない。壊されてしまうものはその人にかかわる、その人を大切に思うすべての人の人生です。

今作は区切りをつけようとする人が多く出てきます。
そろそろ疲れたから、もうかかわりたくないから、会の目的は達成されたから、自分の役目はおおよそ終わったから。
そもそも今作も、いわゆる告発映画でのゴールとなる”告発そのもの”はOPで完了しています。訴えを起こして始まっている。
この作りはそのまま、こうした暴力には終わりがないことを示しています。作品自体の構成が、この事件の終わりのなさを伝えているんです。
告発すればいいわけでもなく、世間の注目を十分得れば終わりでもなく、捜査開始も起訴も区切りにはならない。
死ぬまで一生、そして亡くなったとしても周りの人間は影響を受けて生き続ける。
もしも終わりが来るのだとすれば、それはアレクサンドルの言うような”教会の進化”が果たされたときでしょう。
フランソワ・オゾン監督は実話をセンセーショナルさや社会的距離を持たずに、人の生に起きた暴力として描き、その忌わしく広がっていく影をも照らします。
実に濃厚ですが、展開があっという間でもあり、2時間20分感で問題を自分事にできる秀作でした。
こちら是非劇場で鑑賞を。
感想は以上となります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
それではまた次の映画感想記事で。


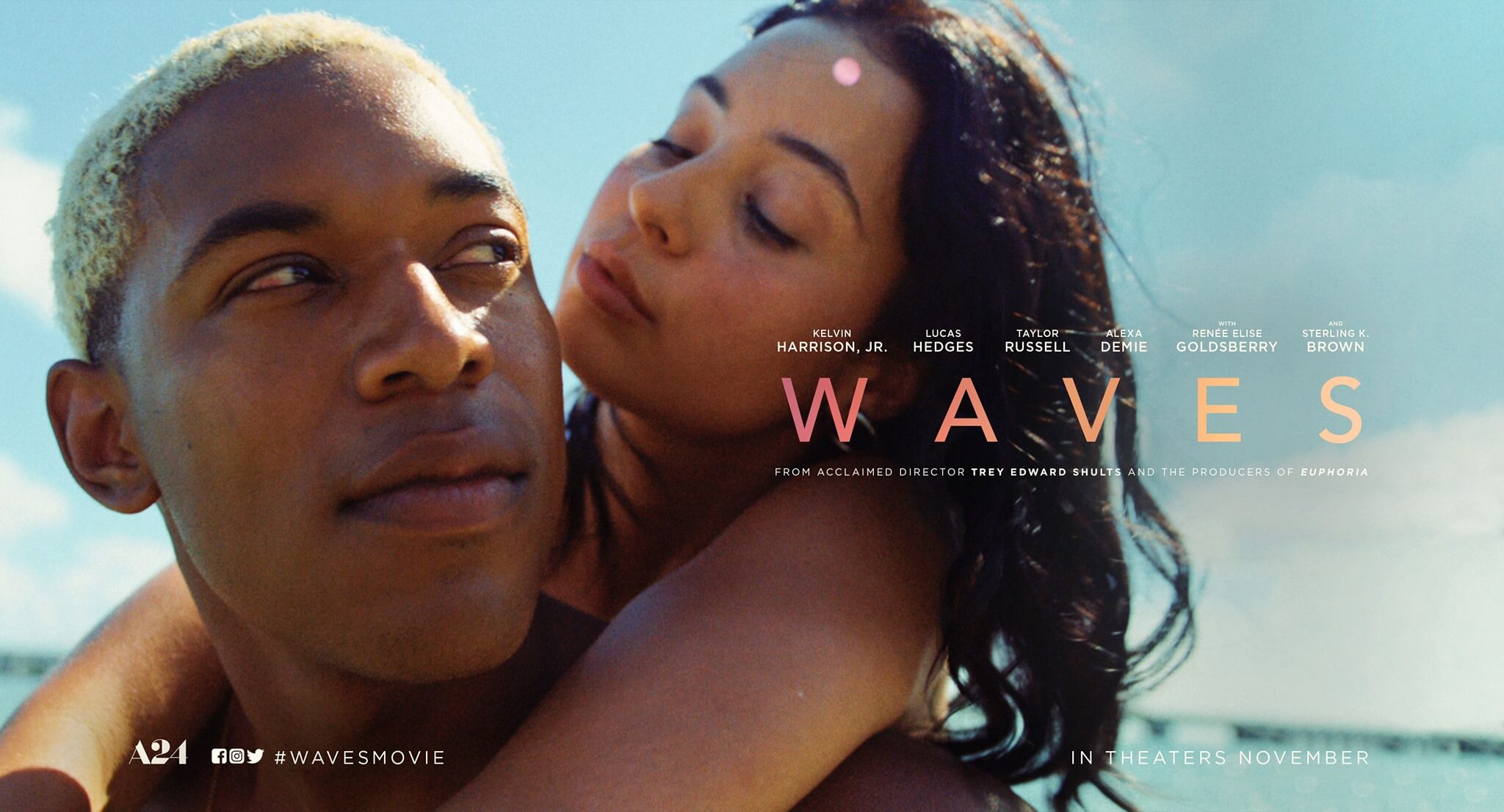

コメント