作品解説

ヨルゴス・ランティモスが監督を務め、主演にエマ・ストーンを迎えた誘拐サスペンス。ランティモス監督とエマ・ストーンはこれで5度目のタッグを組んだことになります。
原作は2003年の韓国映画「地球を守れ!」で、本作はその大胆なリメイクとして制作されました。
プロデューサーには「ミッドサマー」などで知られる映画監督アリ・アスターが参加。ランティモス特有の不条理なユーモアと心理的緊張感が融合した、独自のサスペンス世界が展開されます。
ストーリー設定とキャスト
物語の中心となるのは、陰謀論者に誘拐され監禁される女性ミシェル。エマ・ストーンは本作で丸刈り姿を披露し、極限状況に置かれる主人公を体当たりで演じています。
彼女を宇宙人だと信じ込む誘拐犯役には、「シビル・ウォー アメリカ最後の日」のジェシー・プレモンスと、新人俳優エイダン・デルビスが起用されました。
映画祭と評価
本作は2025年のベネチア国際映画祭コンペティション部門に出品され、さらに第98回アカデミー賞では作品賞・主演女優賞を含む計4部門にノミネート。
監督の作品としてはいつものことですが、国際的にも高い評価を受けています。
監督の作家性とのつながり
ランティモス監督は「哀れなるものたち」、「女王陛下のお気に入り」でも、人間の欲望や権力構造をブラックユーモアで描いてきました。
本作もまた、支配と信念、現実と妄想の境界を揺さぶるテーマを引き継いでおり、監督の作家性の延長にある作品だと思います。
ランティモス監督の新作ともすれば非常に楽しみですし、各映画祭やゴールデングローブなどの前評判としても注目でした。早速公開した週末に観に行ってきましたが、朝早い回になり。でも結構人が入っていて混んでいました。
~あらすじ~

世界的製薬企業を率いるカリスマ経営者ミシェルが、突如として何者かに誘拐される。
犯人は、彼女を“地球侵略を企む宇宙人”だと信じ込む陰謀論者テディと、その思想に心酔する従弟ドン。2人はミシェルを自宅の地下室に監禁し、人類への干渉をやめるよう迫る。
荒唐無稽な主張を冷静に退けながら、隙を突いて状況を打開しようとするミシェル。
しかし、互いに譲らない心理戦は次第にエスカレートし、密室の緊張は高まっていく。
やがてテディの封じられていた過去が露わになることで、常軌を逸した誘拐劇は思いもよらない方向へ転がり始める。
感想レビュー/考察

原作との関係とリメイクの視点転換
今作はヨルゴス・ランティモス監督の新作ではありますが、実はリメイク元は2003年の韓国映画「地球を守れ!」。
実に20年以上前の作品を原作にしていますが、間違いなく現代の社会にも刺さる作品になっています。
少し原作について話しますが、ほぼ今作とストーリーは一緒です。
今作のほうがさらに結末として厳しいものをビジュアルで提示している感じでしょうか。そして、大きく違うのは主人公が誰であるかという点です。
原作の「地球を守れ!」でも大手製薬会社の社長を、陰謀論者が拉致していく話。
少し刑事とか主人公の彼女?的存在も出てきますが、主人公は陰謀論者の方です。なので今作でいうとジェシー・プレモンス演じるテディが主役になっていたのです。
ただ今回のリメイクでは製薬会社の社長が主人公としてメインの視点を置かれています。
社長の性別は原作では男性ですが、今回のリメイクでは女性になっていてエマ・ストーンが演じています。
時代のアップデートで、巨大企業のCEOが女性ということとか、ランティモス監督がこれまでも描いた女性の視点や権力構造にも通じているのかと思います。
陰謀論の時代における皮肉
また視点が社長側にあるのは、現代の世界中で陰謀論が渦巻いているからこそ、プロットの仕掛けも含めて、その怪しさを持っておきたかったからかもしれません。
主人公である場合には、ほとんどの場合にはそれが絶対に正しいという前提に立つことになりますから。
リメイク元でもそうですし、「陰謀のセオリー」(1997)なんかはよく覚えていますが、やっぱり主人公になるだけで、正しいことになる。
ここをあえて入れ替えることで、変人、ネットの見過ぎのヤバい奴感を強めて、現代社会の皮肉みたいなものを入れ込んだのだと思います。
原作と改変については大きく変えていないという認識のもとで、ランティモス監督がこれまで持っていた変態性のようなものはかなり控えめになったかもしれません。

美術と画面設計が語る心理
といっても一定の作家性とか画面構成におけるこだわり、美しさのなかに現れる鮮血と暴力。スタイリッシュなような、ややグロテスクな。
「哀れなるものたち」や「憐みの3章」ほかランティモス監督ともコンビを組み続けているロビー・ライアンによる撮影。
やや正方形よりの画面、クリーンで無機質にも見えるミシェルの邸宅、そして会社。対比するように煩雑で雑多なテディの家。
無機質さがエイリアン=人間らしさがないという意味での美術設計にも思えますし、テディが精神的にも混乱しているそのままの様子を示す家の美術かもしれないですね。
テディの家の中にはハチを示すような正六角形、ハニカム構造がちょことちょことちりばめられているのもポイントです。
映像美術の楽しさもありますが、私は全体にバランスが見事だなと思います。ここで語られていることは、プロットが20年前の映画からあまり変わっていないこともあってか、そこまで自フレッシュではないです。
そしてランティモス監督のオリジナル脚本ではない以上、いつもの突飛さや独特の世界観も弱まっていると思います。

主演二人の演技が支える緊張感
それでもなお楽しんでいけるのは、主演の二人の役者があまりに素晴らしいことと、彼らと演出の妙で生まれるバランスのおかげだと思うのです。
結末としては、陰謀論者であったテディの予想通り、ミシェルは宇宙人でした。アンドロメダ聖人の女王であり(ここにも女王ハチ的な要素が)、本当に地球人を観察し審判を下そうとしていたのです。
ただ、そうは予想こそできても、迫真の演技から、ミシェルは絶えず、エイリアンだと決めつけられた人間の女性に見える。
この状況で否定を続ければ酷いことになるからと、テディの言うことに乗って、自分がエイリアンだということでなんとか最悪の事態を避けようとサバイブする女性にちゃんと見えるんです。
最後の最後まで、テディの陰謀論のままに演じて、逃げ道や解決を探る。そのある意味での演技の中での演技はエマ・ストーンが迫力と繊細さでみせてくれています。
今作でエマ・ストーンは坊主頭を披露しますが、車内での借り上げシーンはまさに一発撮りらしいですね。複数カメラを用意しながら、実際に彼女の髪を借り上げていったということで、まさに体当たり的な入れ込みようですね。

狂気と同情のあいだにいるテディという男
さらに相対するジェシー・プレモンスもさすがの手腕です。
たしかにテディはヤバいやつなんです。大手企業CEOをエイリアンで、人間を支配しに来ているんだという。その陰謀論を人生の軸にして生きているし、従弟まで巻き込む。
だからヴィランとして見れるけれど、でも精神的不安定さの根源を探るとき、同情もするし入れ込んでもしまう。と思えば衝撃的な残忍さを持った異常殺人鬼でもあり、かなりゆさぶりをかけてきます。
そんな二人の関係性と、ランティモス監督お得意の権力構造のシフトは、会話、大量のセリフに依存して展開されます。
だからこそ、それをデリバリーする二人の主演が素晴らしいおかげで、説明会話劇にはならずにスリリングで、最後までノッて行けるんだと思います。
新人エイダン・デルビスの存在感
ちなみにドンというテディの従弟を演じたエイダン・デルビスにも注目ですね。自閉症スペクトラムという設定の人物を、実際に自閉症スペクトラムの方が演じるという試みですが、演技経験ゼロの彼が見事に演じる。
緊張が強まった食事シーンで、いきなり「トイレ行っていい?」と言い出すのは彼のアドリブらしいです。巧いなぁ。

陰謀論と孤独の現代性
紐解かれていく真相。
人類への実験により植物状態となった母。一人深層を感じ取り突き進む息子。ただ現代でもそんな妄信的な人間は陰謀論者、社会的には危険人物とされる。
いま私たちは様々な陰謀論にさらされている。
それは直近でアリ・アスター監督が「エディントンへようこそ」で描いたように、コロナ禍以降急速に肥大化し、いまや私たちはフェイクニュースに、AI生成の画像/映像、それらも飲み込んだ”何を信じたらいいか分からない不安の渦”に生きているのです。
そんな環境で、愛する人を失ったり愛を得られなかったり、孤独を強めれば、強烈でも陰謀論のようなのめりこめる軸に傾倒していくものです。
なんとなく、テディのことをバカにはできないなと思います。原題の誰しもがなりえる存在なのかと思います。
ただ今作は、そこで終わってはいけないという警鐘を鳴らしているのだとも思います。
テディは自分を閉ざして、陰謀論にのめりこみ突き進んだ。普通に生活はできるのに、心を閉ざした対話拒否もする。結果、アンドロメダ聖人の女王だったミシェルに完全に失望され、地球上での人類の指導を止めることに。
ここで地球が平面に描かれているのもまた皮肉なもんですが、その地球から人類を抹消するのです。

人類滅亡エンドに残るわずかな希望
OPと呼応する形で、花とミツバチのクローズアップで締めくくっていく今作は、人類全滅エンドではありますが、ただ冷笑しているわけでもないと感じ取りました。
ランティモス監督は、地球が爆発して消し飛ぶというオリジナルのエンディングとは異なり、機能停止した人類がたおれている地球を映して締めくくります。
タイトルのブゴニア。古代ギリシャの言葉で、牡牛からの誕生/死からの再生を刺しています。血を流さずに死んだ牝牛からミツバチが生まれて反映していくという意味らしいです。
ということは、人類は牝牛なんでしょうね。そこには失敗した人類がいますけれど、ハチもいる。ここからまだ再生していけるという少しの希望も見て取れるラストでした。
ランティモス監督作品群の中では、「聖なる鹿殺し」とか「哀れなるものたち」ほどのシニカルさや独自の世界観はない。「女王陛下のお気に入り」みたいなアクセスの良さには及びませんが、そちらに近しいのかと思います。
原題の人間の問題を冷ややかにとらえつつ、小さな舞台の中で権力構造がシフトする様をスリリング描き、立派な主演二人のやり取りで集中させる秀逸な作品でした。
ランティモス監督もほとんど毎年新作を撮って公開しているので、今後もまだまだその世界を見せて行ってほしいですね。
今回の感想はここまで。ではまた。

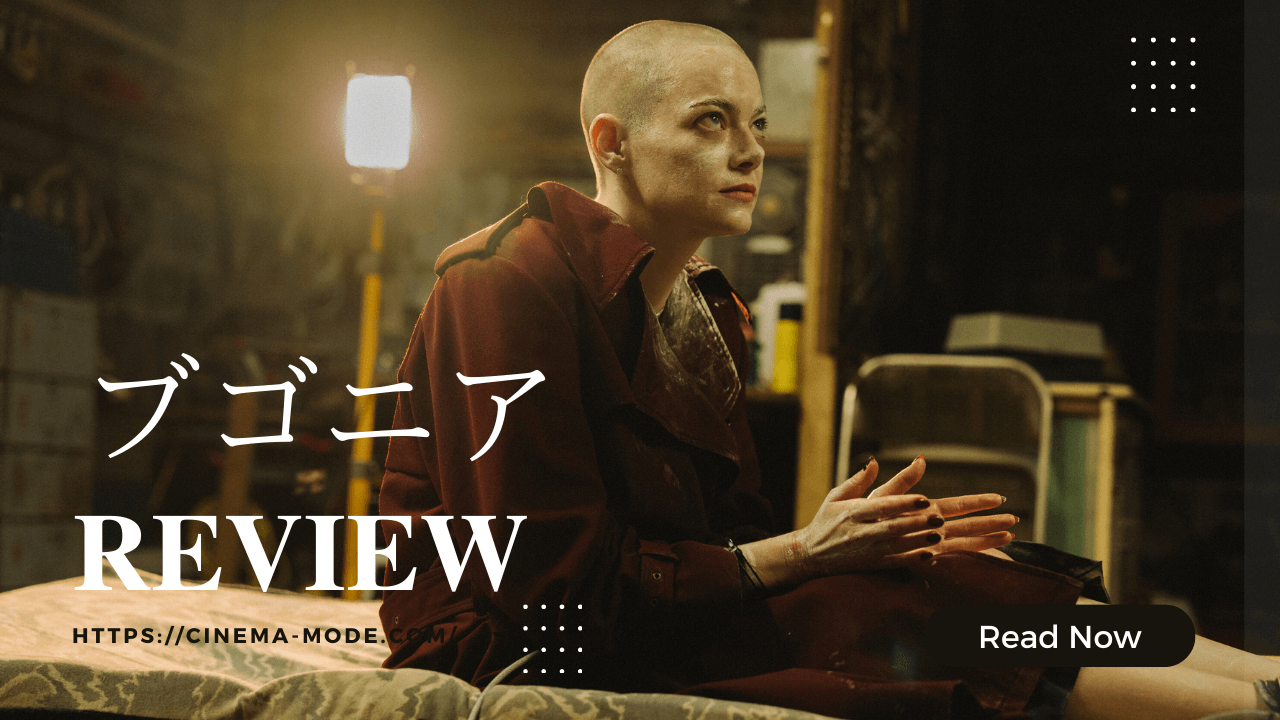

コメント