「夜明けの祈り」(2016)
- 監督:アンヌ・フォンテーヌ
- 脚本:サブリナ・B・カリーヌ、アリス・ヤビル、アンヌ・フォンテーヌ、パスカル・ボニゼール
- 原作:フィリップ・メニヤル
- 製作:エリック・アルトメイヤー、ニコラ・アルトメイヤー
- 音楽:グレゴワール・エッツェル
- 撮影:カロリーヌ・シャンプティエ
- 編集:アネット・デュテルトル
- 出演:ルー・ドゥ・ラージュ、アガタ・ブゼク、アガタ・クレシャ、バンサン・マケーニュ 他

「ココ・ヴァン・シャネル」(2009)のアンヌ・フォンテーヌ監督が、実在する医師マドレーヌ・ポーリアックの戦時の体験をもとにして作られた作品です。主演には「呼吸 –友情と破壊」(2014)のルー・ドゥ・ルージュ。
マドレーヌのことは知らずに鑑賞。後に調べましたが、フランス語wikiだったので欠片くらいしか分からなかったwでも、今作を見れば彼女がした大きなこと、勇気は分かります。
劇場鑑賞が遅れてしまい、初週には観れませんでしたが、この前の連休に鑑賞。で、満員だったのですよ。まあサービスデイってのもありましたけど、久々に満員の劇場体験だったと思います。

1945年のポーランド。戦争の混乱が残る地で、赤十字の病院で働くマチルドがいた。
ある日彼女のもとに、一人の修道女が助けを求めてやってくる。必死に祈る彼女の姿に、マチルドは田舎にある修道院へ行くことを決意。そしてそこで、妊娠した修道女たちのお産を手伝うのだ。
何故修道女が妊娠しているのか。そして母体と赤ん坊のためにも医療の助けが必要なのに、それを拒んでいるのか。
マチルドは激務の合間に修道院へ通い、交流を深めていく中でおぞましい真実を知り、苦しむ修道女たちに自分の力を捧げていく。

実在の医師マドレーヌ・ポーリアックの体験をもとに製作された本作は、彼女の体験を観客に共有させつつも、この時代に置かれた修道女たちの心理描写まで細やかに感じ取らせてくれるものでした。
今作はまさに、思い起こす機能が素晴らしく構成されていて、映像を通して人に共感するという点で私はとても好きです。
事実は既に観客に(実際の話を聞いているまたは、予告を観ても)知らされているなかで始まる本作は、その画面上には具体的に何が起きたかを見せません。
それは口に出すのも、思い出すこともおぞましい、悲惨な過去だからですが、それをそのまま映画の手法として取り入れていますね。
修道女の反応は殻に閉じ籠ったように固く、あまり話さないこともあり、観客は彼女たちの表情から想像していきます。
マチルドの認識の変化が、直接観客の認知とシンクロしているのが上手いと感じました。
彼女が修道院に通い始め、やはり現実と信仰の衝突が起きます。彼女からすれば、頑なに口を閉ざし援助を受けないことははっきり言って理解できず、愚かしく思われます。
この時点では私も観ていて、信仰も大事だけど、命はもっと大事だろうに。と思っていました。
しかし今作は「凌辱されたのは分かるけど・・・」というシーンの次に、決定的な場面を持ってきました。
あの夜道です。あれが全てを変えました。心底怖かったし、とてつもなく不快でした。分かったようなことを言っていて、何も分かっていなかったのです。マチルドは未然で済みましたが、修道女たちにはあれが実際に起きた。
その後マチルドはあの夜道での事は一切口にしません。
自分でも言いたくないし、思い出したくない事に、修道女たちは常に向き合っていたということです。しかも彼女たちは信仰に揺れ罪の意識にすら苛まれているのです。

マチルドは夜道で引き返し、修道院で夜を明かしますが、朝目覚めてのショットが素晴らしかったです。現実を知り絶望したような彼女がベッドに横たわっていますが、ここで壁に掛けてある十字架がちょうど画面内に納められています。序盤では軽く見えていたものが、ここに来て心底救いと希望に変わった瞬間です。
マチルドがプロとしてではなく、友人のように接し始めると、同じ僧衣でほとんど見分けがつかなかった修道女たちにも、個性が見えてきます。彼女たちのそれぞれの信仰、事件との向き合い方、過去や将来の事。
そこでまた辛い事実が明らかになっていくのですが、少しでも癒しを得ていくのが観ていて嬉しかったです。
初めは厳しく感じたシスター・マリアとの少しづつの友好も、撮影で示されていましたね。二人を前後に配置、並べて配置、そしてピントがどちらにもしくは両方に合っているのかなど、徐々に同じ空間に収まり始める関係性が巧みでした。
夜の闇に灯りを持ってきたマチルド。暗かった夜により多くの灯りが灯され、音楽が流れ始める。革命的とまでいかずとも、人に共感し理解し始めたマチルドは芯が強く、自分の意志ですべき事をしていきます。

自分の意志で動く自立した主人公マチルドを演じるルー・ドゥ・ラージュも、シスター・マリア演じるアガタ・ブゼクも、そして院長であるアガタ・クレシャも、皆繊細な良さと表情を持って、感情の爆発をさせずとも十分に観客に強烈なエモーションを与えていました。
中でも院長は、今作で微妙な立場に置かれるため、憎まれそうでしかし彼女の守りたかったものも分からなくはない、絶妙に悪といえない切なさがありましたね。
原題は「罪なきものたち、無垢なものたち」という意味ですが、今作は多くの被害者が登場していますね。何かが起きてしまってから、生き抜いてきたものたちです。
同僚の医師もホロコーストの生存者でありますし、何気なく冒頭から顔をみせているのは、戦争孤児たちです。
子供というのは無垢の象徴ですが、今作には究極の無垢である赤ん坊の存在が大きいでしょう。
経緯はどうであれ、彼らを救うことで1つにまとまっていく。ポーランド人もフランス人もそして最後はユダヤ人も関係なく、皆で協力していきます。
戦乱の最中行われた凄惨さは、直接見せられることはありませんが、十分に感じとり想像することができます。信仰に関わらず、何かここだけは守らなければいけないはずのものまで蹂躙されてしまった痛みは、完全に分かることはないでしょう。しかし、今作は共感させることに成功しています。
全編を通し暗く寒く色のない修道院に、最後は優しい陽の光が差し込み、マックス・リヒターによる”The Nature of daylight”が流れたところですごく感動していました。
残酷で重い背景ながら、それを共感する作りで丁寧に伝えつつ、光を与える作品。
言葉も価値観も分からなくとも、痛みは分かる。それを共有し癒すために勇気をみせるマチルドを通して、私も救いを見たと感じました。かなりおススメの作品。
というところで、今回の感想はおしまいです。修道院舞台の映画ってあまりみたことないのですが、おもしろい作品が多いのかな。それでは、また。



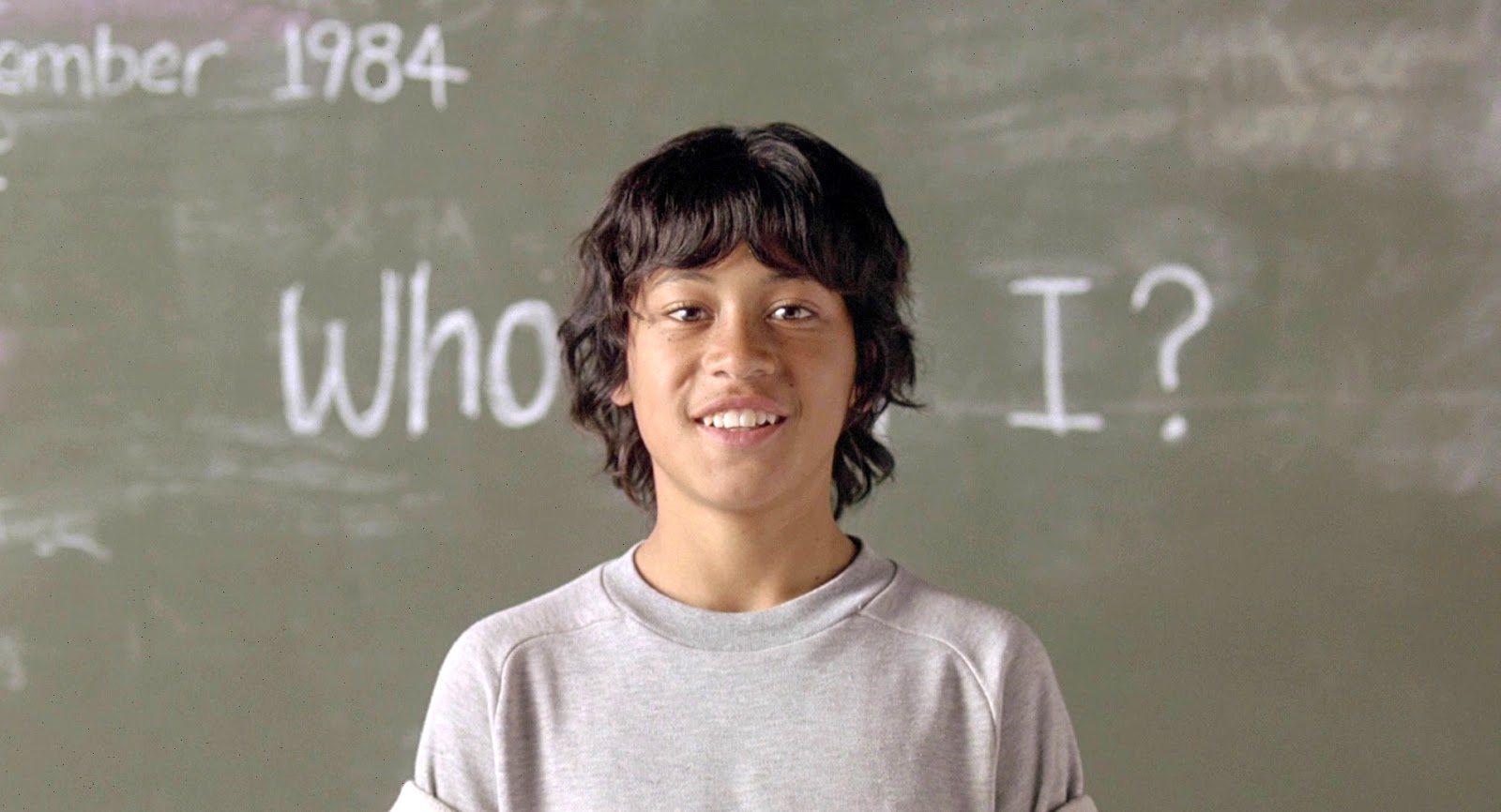
コメント