「グリーン・ブック」(2018)
- 監督:ピーター・ファレリー
- 脚本:ニック・バレロンガ、ブライアン・ヘインズ・クリー、ピーター・ファレリー
- 製作:ジム・バーク、ピーター・ファレリー、ニック・バレロンガ、ブライアン・ヘインズ・クリー、クワミ・L・パーカー、チャールズ・B・ウェスラー
- 製作総指揮:ジェフ・スコール、ジョナサン・キング、オクタヴィア・スペンサー、クワミ・L・パーカー、ジョン・スロス、スティーヴン・ファーネス
- 音楽:クリス・バワーズ
- 撮影:ショーン・ポーター
- 編集:ポール・J・ドン・ヴィトー
- 美術:スコット・プラウチ
- 衣装:ベッツィー・ヘイマン
- 出演:ヴィゴ・モーテンセン、マハーシャラ・アリ、リンダ・カーデリーニ 他

「メリーに首ったけ」(1998)などコメディ畑で知られるピーター・ファレリー監督作。今回はボビーはおらず一人での監督ですね。
扱うのは実在のピアニスト、ドクター・シャリーと、彼と友人だったトニー・バレロンガのアメリカ南部への旅。それぞれ「ムーンライト」のマハーシャラ・アリ、「はじまりへの旅」のヴィゴ・モーテンセンが演じ、両者アカデミー賞にノミネート、アリが助演賞を受賞。
また、今作は作品賞、脚本賞も受賞している作品です。作品賞受賞効果もあってか、初週から満員でした。けっこう幅広めの客層で、笑いが絶えない劇場でしたよ。

ニューヨークのナイトクラブで働くトニー。粗暴で腕っぷしの強い彼は、面倒を起こす客などのトラブル解決が得意だ。
しかし、働いていたナイトクラブが一時閉店となったため、つなぎの職を探すことになる。そこでトニーに声がかかった仕事は、ドクター・シャリーという男の運転手だった。
面接に行ってドクターが黒人だと知り驚くトニーだったが、ドクターからの願いで仕事を引き受けることに。仕事は8週間。ピアニストであるドクターの南部でのコンサートツアーに同行することだ。
黒人が南部で安全に過ごすのは難しい。黒人向け宿の案内書”グリーン・ブック”を片手に、トニーとドクター・シャーリーは旅へ出発する。

アカデミー賞作品賞受賞、また人種差別を扱った実話ベースの物語ということで、若干身構える方もいるかもしれませんが、その心配はありません。
ピーター・ファレリー監督はコメディで活躍していた方で、今作も例にもれず彼の手腕が効いていて、全編通して笑いに包まれたコメディドラマとして楽しく見れるかと思います。
ちょっとでも気になっているという方はぜひ気軽に観に行ってください。
実際私もたくさん笑いました。で、その笑顔で観られるスタイルというのは、とても親しみやすく良かったかなと思います。今回扱われている差別に関しては、実際にこのトニーとドクター・シャーリーの二人と一緒に過ごしていき、その上で体感していく必要があるからです。

過去の特定の時代の人物ドラマとして観客と距離を置かせていては、あくまで遠い国の過去のお話になってしまったかと思います。
子供っぽいところのあるトニーと、ちょっと世間知らずなドクターのやり取りにはほんのり偏見の要素も取り入れられていて、笑いながらも”そういう背景もあるんだな”と感じます。
フライドチキンの下りなんかは車の中での会話、ポイ捨て問題、その後の夕食会と、あれだけで二人の親密さと黒人とフライドチキンの関係またはそれに対する白人社会の偏見までつながっている上手い脚本家と思います。
実際のところ、フライドチキンと言えば確かにハーレムのイメージがあって、聞いたところによれば奴隷制時代または自由黒人ですら、豚や牛を飼うお金がなく、唯一買えたのが鶏であったとか。
それでフライドチキンを作り商売するしかなかった。だからフライドチキンは結構センシティブな食べ物ということです。
実際この作品は、差別描写がぬるいという批判がありますが、個人的にはそうは思わなかったです。確かに表面上はドギツイわけではないです。
しかし私にとっては酒場や警官のモロな差別よりも、一見優雅で教養人に見える白人たちが、ドクター・シャリーを迎え入れつつも暗黙の了解で線引きをしているその感じが非常に不愉快で、とても効果的だなと思いました。
町自体がそういうものなんだと、染みついていて、もはや誰もおかしいとさえ思っていません。
無意識の差別もそうですし、地域性だからとか真っ当な言い訳みたいなことを言い出す、その不当さとあえて自分個人は悪くないみたいな感じがとても胸糞悪い。

そんな胸糞悪さを、トニーも次第に感じていくのが良いところ。
オープニングではグラスを捨てていた彼が、ドクターのことで怒り始めるわけで、特に支配人に「お前だって金のためだろ。そうじゃなきゃあんな奴・・・」って言われて我慢できなくなるのが優しくて素敵です。
あの時点でもう、トニーはボスだからとか週給125ドルだからとかではなく、ダチのために運転してるんですよね。
2人の距離が詰まっていく。トニーは手紙のコツを覚え、ドクターは自分を見つけていく。自分が何者なのか。トニーは絶対的、ドクターは常に相対的でした。
ですが、白人好みのポピュラーミュージックではなく、ショパンを好きなだけ弾き、そして楽しく一体となってルーツであるジャズセッションを楽しむ姿は、本当に生き生きとしています。

ここまで心地よいといっておきながら、自分としては実は安易だとも思っている作品です。
心地よさが出来すぎといいますか。実際のところ、白人の救世主だとまでは言いませんが、お話自体はオーソドックスで、演出もまあ普通で、ちょっと昔のいい感じの映画。
奥深くに突き刺さってくるとか、ユニークで愛に溢れているとかって程でもないかな。
それでもこの作品を見ながら、笑って泣けるのって、やっぱりヴィゴ・モーテンセンとマハーシャラ・アリのおかげ。
この二人に本当に感謝です。二人の演技がこの友情を、実際はどうであったにせよ、この作品、スクリーンの中では本物にしてくれています。
人によっては怒るかもしれないちょっとぬるい感じとか、そもそも一昔前の黒人への配慮映画みたいなところはぬぐえませんが、私個人的には主演二人がとっても輝いていたので満足な作品でした。
作品賞かって聞かれると、即答できませんけれど、軽いタッチで誰でも見やすいのは確かなので、是非劇場で鑑賞してください。感想はこのくらいで。それではまた。



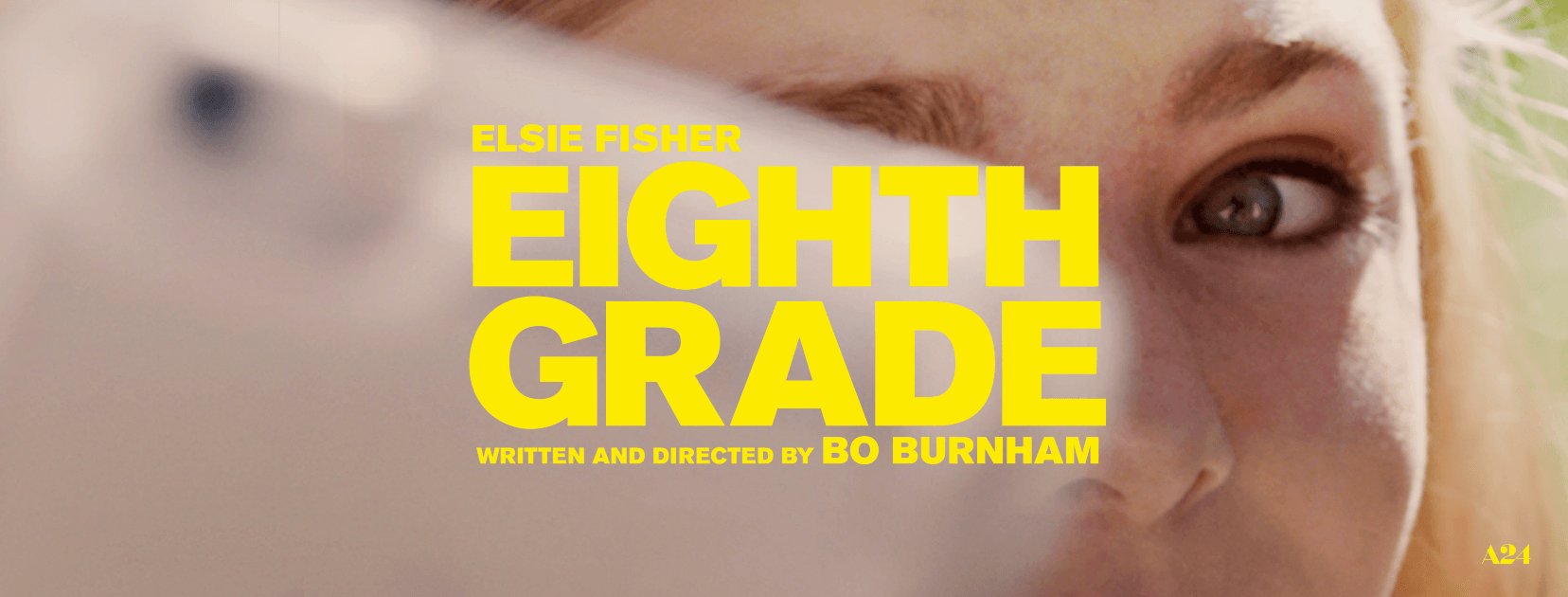
コメント