
作品解説
- 監督:アンダース・ウォルター
- 製作:ミリアム・ノルガード、メッテ・ホスト・ハンセン、トマス・ラドアー
- 製作総指揮:ヘンリク・ツェイン
- 原案:ミリアム・ノルガード、アンダース・ウォルター
- 脚本:アンダース・ウォルター
- 撮影:ラスムス・ハイゼ
- 美術:ハイディ・プラッゲ
- 衣装:エミリー・ボーゲ・ドレスラー
- 編集:ラース・ビッシンク
- 音楽:ヨハン・セーデルクビスト
- 出演:ピルウ・アスベック、カトリーヌ・グライス=ローゼンタール、モルテン・ヒー・アンデルセン、ラッセ・ピーター・ラーセン、ペーター・クルト 他
第二次世界大戦末期、ドイツからデンマークへ押し寄せた20万人以上の難民という歴史的事実に基づき、極限状況の中で信念を貫こうとする家族の物語を描いた感動的なヒューマンドラマ。
監督・脚本は「バーバラと心の巨人」のアンダース・ウォルター。「ある戦争」や「サマリタン」のピルウ・アスベックが父ヤコブ役を務め、本作で長編映画デビューを果たしたラッセ・ピーター・ラーセンが息子セアン役を演じています。
デンマークが舞台の映画ですけれども、ナチス占領下から解放のあたりを描いていることと、ドイツからの難民が来ていたことなどあまり知らない題材に興味があって鑑賞してきました。
公開した週末に地元の映画館へ行ってきたのですが、そこまで混んではいなかったですね。
~あらすじ~

1945年、ドイツ占領下のデンマーク。市民大学の学長ヤコブは、敗戦寸前のドイツから逃れてきた多くのドイツ人難民を学校に受け入れるよう、ドイツ軍司令官から命じられる。
はじめは200人と言われていた難民も、到着してみれば500人を超えており、学内の体育館は箱詰め状態になってしまった。デンマークはナチス占領によって被害にあっていたため、あくまでも避難場所の手地経だけを行い、ドイツ人への支援を行うことはしたくないという声が多い。
しかし、避難民たちにはドイツからの食糧支援などがなく、多くが飢餓状態に陥っていた。さらに追い打ちをかけるように、ジフテリア感染が発生しており、ドイツ人難民たちはヤコブに助けを求めてきた。
一家がドイツ人難民を助ければ、周囲から裏切り者と見なされ全てを失う恐れがあるが、拒めば多くの難民が飢えや感染症で命を落とすことになる。
揺れ動く父の心やナチスによって家族を殺されたデンマークの町の人たちを、ヤコブの息子セアンは心配に眺めていた。
感想レビュー/考察

分断される大人たちを、軸を決めきれない子どもの視点から描く
大きな力のあるルールや圧力、また争いのもとでは人は分断されてしまいます。異なる意見を持つ人達が互いを牽制し、時に攻撃し、傷つけ合ってしまう。
さらに潮流が変わることでその攻撃も変化する。それぞれにとっての正義が体制によって力を変えることになる。
分断の中で拠り所を持たない人ほど、そこでとても揺り動かされてしまうことになります。
子どもというのは自分自身でのイデオロギーを持つのは難しいので、大人を眺めながらもがいて、なんとか自分のつく側を見定める。
仲間外れが嫌でとりあえずどちらかの大きなグループに入ったり。良いと思ったことが思ってもいない結果を招いてしまったり。
今作は終戦間近である時間を切り取り、そこで大きく分断されていく大人たちを、その中でもがいて自分の思いを固めようとする子どもの視点から描き出しています。
どちらかの側を悪役にはせず批判しない
だからこそなのか、今作では(ナチスドイツは除いて)どちらの側についている人間に対してもそれが善とか悪とかの判断はしないで、批判をせずに観察をしているようなスタンスを感じます。
実は父も母もすこし強引だったり、独りよがりさを感じます。その人道的な立場は評価されるものですが、直線的が過ぎるようにもみえるのです。またビルクについては彼の父がナチスに殺されたという背景があるものの、ある種手段を択ばない攻撃性は恐怖を感じます。
ナチスに所属するドイツ人医師でさえ、二面性がある。誰しもに理由がありドラマ的な展開があるので、一辺倒に”悪人の中で奮闘する人道的な家族”にはなっていません。
主人公がセアンという子どもなので、彼の視点から見ることでより公平というか、揺れ動き方が大きく感じられました。

人道だけでは進めないOPの衝撃
1940年4月9日にナチスドイツがデンマークを占領し、この作品の舞台は1945年なので5年間の間ナチスの占領を受けている。
映画の冒頭ではセアンが医師の元診察を受けていますが、その医師がレジスタンスに手を貸していたことがナチスにバレてしまい、玄関先で射殺されます。こんな理不尽な暴力の横行する(そして特に正義はなされない)デンマークの状況がここでしっかりと示されます。
OPすぐにこの衝撃的なシーンを入れることで、ナチスの非道さとか、レジスタンスはじめ町のデンマークの人たちのドイツへの嫌悪感が理解しやすくなっています。主人公もドイツに対して怖さと敵対心を持ちやすい状態になります。
実際、デンマークではナチスに反してユダヤ人の救出を行っていたこともあるようで、そのあたりも含めて、反ナチと人道的な動きの方が優勢ではあったのかもしれません。
一般市民である漁師たちが、約7,200人のユダヤ人を船で中立国のスウェーデンへ逃がしていたようです。
物語が少し進むと、ナチスドイツの敗戦濃厚に。ソ連の反撃などからドイツの一般市民も多くがナチス占領下の欧州各国に避難している状況。
ただはっきりと終戦が見えているわけではないので、思い切ったこともできず。
そんななかで病気の妊婦や子どもたちをみて、まずセアンの母が人道的に正しいことをしようとする。しかし、それは危険な行為だと町の人間や学校側そして父ですら批判します。
OPのようなことがあって、すぐに人としての正しい行動ができないのも理解できますね。

独特な時期を取り上げる
そこで今作は人道的行動をすることが間違っているという特殊な状況、コミュニティでの大きな転換を描きます。
セアンははじめ、ものすごくドイツ人を助けることに反発する。それはもちろん、自分の担当の先生を撃ち殺した存在であるからですし、コミュニティでも悪いと言われているからです。
しかし、惨状を目の当たりにすると心が揺れる。父も支援をし始めるとき、セアンなりに考えて自分の立場を探すのです。そして父を想うがゆえに、ビルクに話してしまう。決して密告や父を批判してのことではないのですが、それが逆に父の立場を危うくしてしまうのです。
親ナチスとレッテルを貼られた父にならい、セアンもいじめを受けます。辱めを受けた彼は今度は森でドイツ人少女に助けられる。
この時点でかなり拠り所を失うセアンですが、次にはレジスタンスであるビルクに寄り添うことにします。子どもは検閲に引っかからないという理由で、銃を運び始めるセアン。
彼自身がレジスタンスを心から応援しているとか、ドイツ人は殺せばいいと思っているとは感じません。ただ、彼は安心できる居場所が欲しかったと見えました。
転換によってパワーバランスが変わるとき、迫害が生まれる
終戦を迎えることで、さらに大きな転換がされます。親ナチスであるデンマーク人への表立った迫害です。
そういえば「サントメール ある被告」でも流れていた映像として、女性が丸刈りにされて服を剥ぎ取られ辱めを受けながら町を追われる描写がありました。
ドイツ兵と恋仲ないし性的な関係を持っていた女性たちが、終戦後に丸坊主にされているのは、フランスの事例として有名です。このデンマークでも、セアンの学校の友達の母が同じ境遇になります。
以前から陰口やいじめはあったのですが、このように顕在化したのは終戦後です。
人は揺れる。だからこそ思いやりを出すチャンスもある
コミュニティとして父はリンチにあい、居場所を失う。そんな中でセアンはやはり人の命は救うべきだという倫理観を固め、最後は自分の意志でありまた他に目的もなく、ただドイツ人少女を救おうとするのです。
この少女を救う際に、検問所でビルクに出会いますが、彼は少女を見てセアンたちを見逃します。憎きナチスドイツとこのドイツ人少女をイコールで観なかった。
こういった描写が、いわゆる”人の心”なんて安直な言葉では片付かないのが今作の魅力でしょう。時世の流れや立場、見る位置や状況次第で、人間は分断され意見を変えたり行動も変わる。
こんな混沌とした中で、誰しもがセアンのように自分の意志を持たなければいけないのでしょう。そして、セアンのように、そしてビルクのように、揺れ動きながらも、人としての心を見せることはできる。
最後まで無関心ではいられない。どこかで人間は思いやりを出せるはずなのです。
見ごたえがあるドラマですが、人の奥底にある良心を、このような形で描き出すスタイルと物語が興味深い映画でした。
今回の感想はここまで。ではまた。

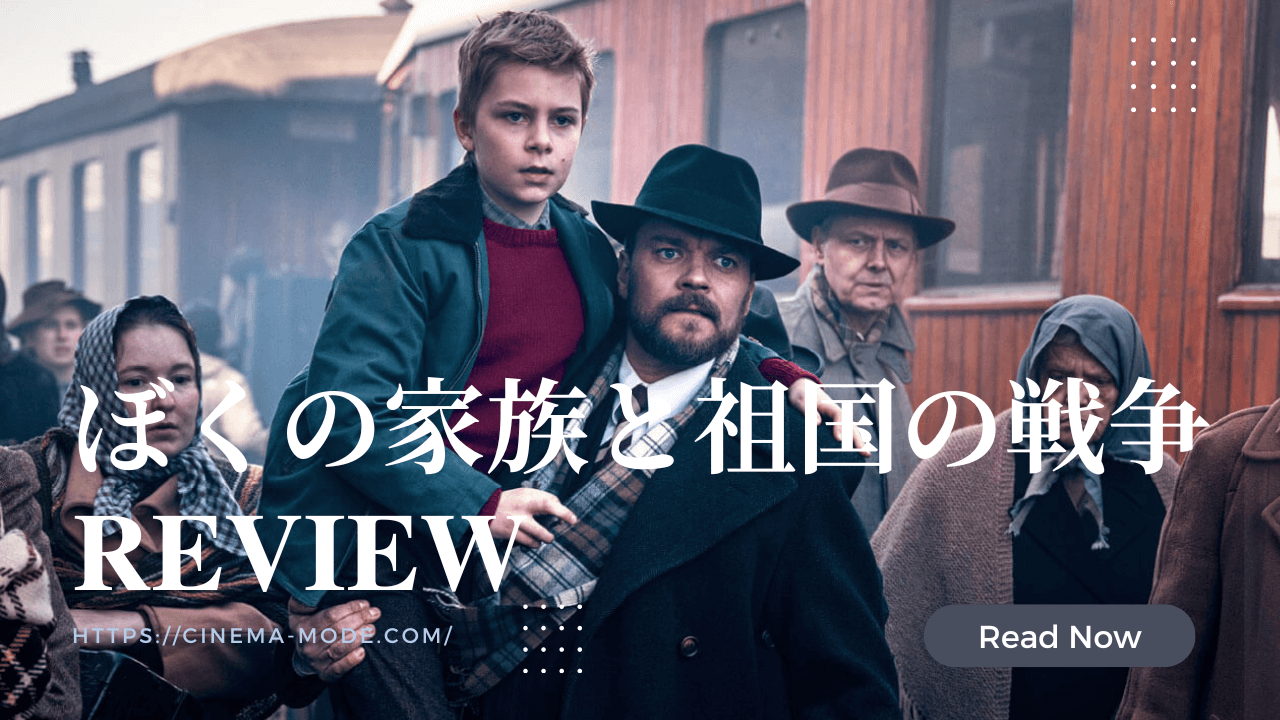


コメント