「12日の殺人」(2022)

作品解説
- 監督:ドミニク・モル
- 製作:カロリーヌ・ベンジョー、バルバラ・レテリエ、キャロル・スコッタ、シモン・アルナル
- 原案:ポーリーヌ・ゲナ
- 脚本:ジル・マルシャン、ドミニク・モル
- 撮影:パトリック・ギリンジェリ
- 美術:ミシェル・バルテレミ
- 衣装:ドロテ・ギロー
- 編集:ロラン・ルーアン
- 音楽:オリビエ・マリゲリ
- 出演:バスティアン・ブイヨン、ブーリ・ランネール 他
「悪なき殺人」などのドミニク・モル監督が、生きたまま焼き殺された少女をめぐる捜査から見えてくる社会の歪みをあぶり出していくクライムミステリー。
モル監督とジル・マルシャンが共同で脚本を手がけ、未解決事件の闇に飲み込まれていく刑事の姿を描きます主人公の刑事ヨアンを「恋する遊園地」のバスティアン・ブイヨン、相棒マルソーを「君と歩く世界」のブーリ・ランネールが演じています。
今作はフランスのアカデミー賞に相当するセザール賞(2022)で、最優秀作品賞、最優秀監督賞をはじめ、見事最多の6つを受賞しました。
本作は、実際のフランスの事件を元にしたフィクションであり、ポーリーヌ・ゲナによる『18.3: Une année à la PJ』が原作です。
公開週末に観てこれなかったのですが、そのあとの祝日に日比谷に言って観てきました。サービスデイということもあったし祝日だったので満員の中で観ることに。
〜あらすじ〜

フランス、2016年の10月12日。
友人の家で遅くまで遊んでいた21歳の大学生クララが、深夜の公園近くで何者かに襲われ、焼死した。
ガソリンをかけられて生きたまま焼き殺されるという残虐な事件に、地元の警察署のチームは操作を始めるも、クララと関わる人物たちは皆怪しい。
誰しもがクララと付き合っていたとも、ただ体の関係があっただけとも言える。
彼女の死を悼む様子のない男たちに憤りを覚えながら捜査は続いていくが、手がかりと思えるものが出ては消えていく状態であった。
感想レビュー/考察

直近に同じくフランス映画で「落下の解剖学」を観たこともありますが、今作は似たテーマというか。
殺人事件の解決に向かって動く捜査班を描く作品ではありますが、ミステリーでも答えのない作品です。答えの出ない無念さに観客を放り出すことで社会的な問題を提議しているのです。
犯人への到達とか対決はないです。これは映画の序盤にすでに示されることになります。
「この映画で描かれるのは数多くある未解決事件の1つである。」つまり解決していないのです。
カタルシスを求めたり、上質なミステリー映画をみたいなら、期待外れということになります。非常にやりきれず出口もなく、辛い旅なのです。
この作品の捜査から見えてくるのは、警察内部にある歪みや機能不全、個人的な事情がいかに捜査に影響するのか。また潜在的にある女性蔑視の風潮です。
観ていてなんとも日本でもよく見かけるような人間、事象が並べたてられるため、苦しいものがあります。
自身も飲み込まれていく二人の刑事
今作で主要な主人公になるのは2人の刑事です。良い警官と悪い警官のコンビをそのままに、リーダーであるヨハンは冷静でどこか一歩引いた距離感すら持っている刑事です。
彼はこの事件から、まるで今までは警察としての仕事がプライベートには影響しなかったものが、クララの一件から自分自身をも変えられてしまうようなドラマを体験していきます。
そしてもう一人の刑事はより粗暴で荒くれ感のあるマルソー。彼は自身の妻が他の男と浮気をして妊娠、結果自分を捨てて相手の男と家庭を持とうというクライシスを迎えています。
ボロボロの彼にとって、クララの事件で出てくる容疑者たちは皆、自分の妻を妊娠させた男に重なる。私情をものすごく挟んで容疑者にあたっていく。

ぐるぐると回るサイクリングコース
2人が事件を捜査するほどに、それに飲まれていく。
特にヨハンがロードバイクをこいでいるシーンが印象的です。
彼はサイクリング用のコース、つまり楕円形の中をぐるぐると走っているだけ。どこにもたどり着けない堂々巡りのこの行為は、まさに彼の捜査そのものを示しています。
彼が走るのが夜だけなのも、事件が闇の中にあり先が見えないことを含んでいるのでしょう。
マルソーはここで抱えきれなくなり途中退場してしまいますが、ヨハンも相当に精神的にもこの事件にはまいってしまう。
警察内部ではかなりのマッチョ体質で、あとから女性の捜査官が追加されて彼女自身が言うように男社会。
そしてその男性社会における女性への抑圧は、捜査の中から嫌というほどに見えてきます。
女性が悪いという風潮、蔑視の社会
クララとかかわりのある人物がどんどんと出てきますが、ロクな男がいません。みんながクララとの関係を体の関係と結び、結婚していたり本命の彼女がいたり。
なによりも同情や悲嘆などという感情が一切見られないのです。ヤってた相手がいなくなっただけ。心からクララのことを想っていたものなんていない。
挙句には直接会った事すらない男まで、ニュースで彼女の写真を見て勝手に思い入れを強めてきてしまう始末です。奔放な女性だと言って、なぜか彼女の性的な交友関係ばかりに着目する。突き詰めるべきは彼女を殺した犯人なのに。
ミステリーとしては檻の中に閉じ込められていますが、ヨハンが言うとおりに「誰もが犯人なのだ」ということ。この男たちみんながクララを殺したと言え、それはつまりこの男社会が彼女を殺したということ。

被害にあった女性が悪いかのような風潮。そんな時間に、そんな場所で、そんな交友関係で。。。殺人があってもまるで彼女こそが責められるべき存在かのように。
これが若い男性だったらどうだったのでしょうか。仮にクララがものすごい優等生だったら?クララを知っているのはあの親友であるナニーだけではないのか。皆彼女を知らないのに、うわべから彼女を判断している。
深い傷だけが残る
残されていくのは両親。残酷な時間の流れからクララのことは忘れ去られそうになるものの、深い傷はそのままに残されていく。
この事件は未解決だからこそ、分からないという無念さが両親にも親友にもそしてヨハン達捜査官にも残されてしまいます。
見えるようで見えない解決の糸口に向かう中で、根深い女性蔑視が露出していく。どの男も犯人なのです。この事件が解決するためには、社会自体が変わっていかなくてはいけないのですね。
革新をついてくるのは、ナニー、女性裁判官、新たに配属された女性捜査官と女性ばかり。
ヨハンが最後、開けた大きな道路を、晴れた昼間にロードバイクに乗って走る姿により、少しだけの解放や希望も入れ込んであると感じます。
「ゾディアック」のような未解決の不気味さに、「ロストガールズ」でも描かれたような女性の被害者への社会的な差別まで感じる秀逸なドラマでした。
なかなかにやるせないので見るのに体力が要りますが、ぜひ劇場で観てほしい作品です。
今回の感想は以上。ではまた。

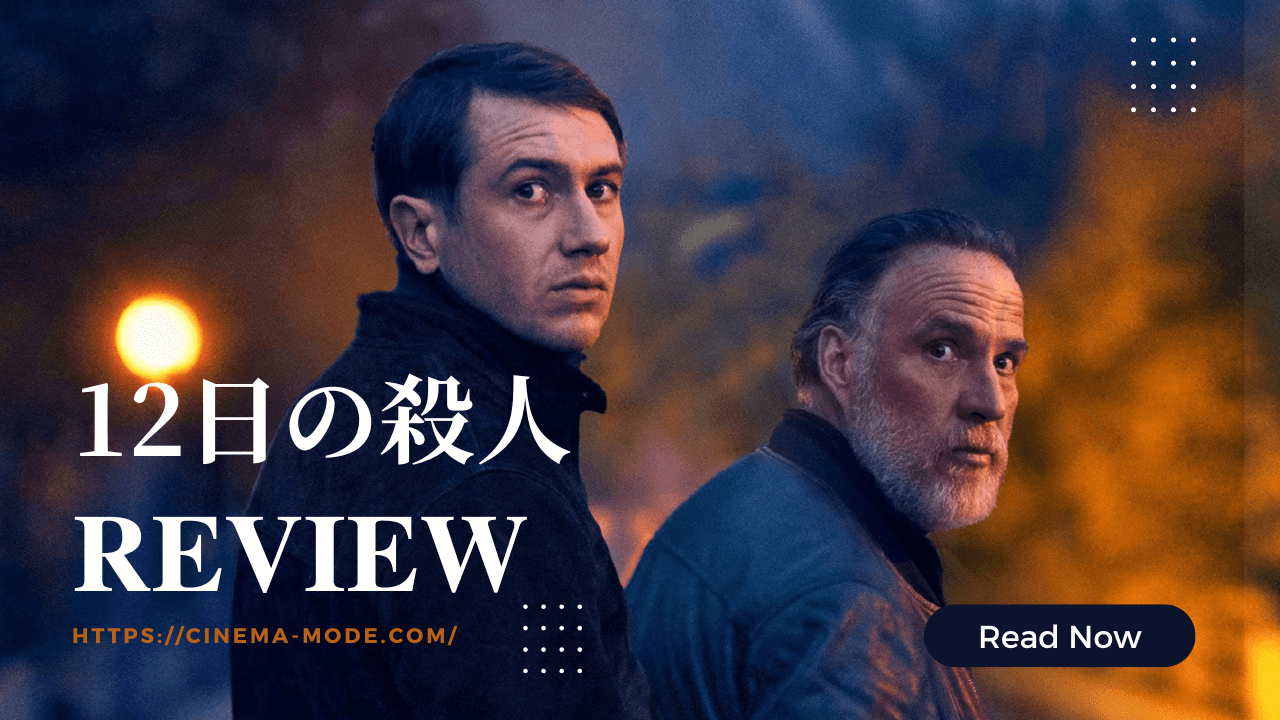


コメント