「20センチュリー・ウーマン」(2016)
- 監督:マイク・ミルズ
- 脚本:マイク・ミルズ
- 製作:アン・ケアリー、ミーガン・エリソン、ユーリー・ヘンリー
- 音楽:ロジャー・ネイル
- 撮影:ショーン・ポーター
- 編集:レスリー・ジョーンズ
- プロダクションデザイン:クリス・ジョーンズ
- 衣装:ジェニファー・ジョンソン
- 出演:アネット・ベニング、グレタ・ガーウィグ、エル・ファニング、ルーカス・ジェイド・ズマン、ビリー・クルーダップ 他

グラフィックデザイナーとしてのキャリアから監督に転じ、「人生はビギナーズ」(2010)などのマイク・ミルズによる最新作。彼にとっては長編映画4本目になりますね。
主演には何度もアカデミーノミネートをしていながら、いまだに受賞には至っていない名優アネット・ベニング。
そして主演と言ってもいい女性を演じる、「ネオン・デーモン」(2016)などの注目若手のエル・ファニング、「マギーズ・プラン 幸せのあとしまつ」(2015)のグレタ・ガーウィグも出演。
ベニングの息子役には10代のルーカス・ジェイド・ズマン。そして「ジャッキー/ファースト・レディ最後の使命」(2016)のビリー・クルーダップも出ております。
今作はアカデミー賞では脚本賞にノミネート。ベニング最高の演技と言われる評判で、個人的にかなり楽しみに待っていた作品。公開日に観に行きましたが、そこそこの数が入っていましたね。まあ次の週には1日2回までしぼんでましたが。
しかしこれは必見案件でございますよ。

1979年のサンタ・バーバラ。
シングルマザーで息子を育てるドロシアは、最近その息子のジェイミーが良くわからなくなってきたと感じる。ある時彼が”失神ゲーム”なるもので意識を失い、病院に搬送されたことでついにドロシアは決意した。
同じアパートに住むフォトグラファーのアビー、ジェイミーより2つ年上で幼馴染のジュリー。この2人に息子の教育をいらいするのだ。
かくしてジェイミーは頼んでもいない新たな保護者に囲まれることになる。そしてそれは、少年にはすこし突飛な教育の始まりだった。

1979年のサンタ・バーバラとは、全く縁もゆかりもないですが、この作品をすごく身近に感じたのがまず観終わった印象でした。
そして同時に、今作が見せる時間の超越と接触、暖かく光る世界がすごく好きになりました。
オープニングの海の俯瞰ショット。そして海を向こうに、通りと街を映す撮影で既に持っていかれました。綺麗だなぁと。
まあ後にも海岸へ言ったりしますけども、命の生まれる海、母を巡る映画にはもっともな始まりですね。
これは監督のある意味自伝というか、ミルズ監督の身近な人間をミックスしたり、経験を重ねたりして描いた作品という事なのですが、監督はそういった個人的なものをそのままの新密度を保ちながら、それでいて普遍的で時間も場所も超越して観る人に寄り添うような素敵なバランスを作り上げていると思います。
どこかに大きな課題があるとか、何か目標のあるプロットがあるわけではありません。
ただ、この時サンタ・バーバラにいた少年と母と、フォトグラファーとティーンと元ヒッピー。彼らがとってもリアルに、そしてリアルタイムに存在する様を眺めるのは、すごく心地いいものでした。
それはもちろん、タイトルの20世紀の女性たちが、20世紀が、今はもう存在しないものであるからかもしれません。
もう体感できないその時を体感するというのは映画らしいと思いますし、すごく輝いていたなと思います。ナレーションをするドロシアがあっさりと自分の死を明かしたり、いつの時点から話しているのかあいまいで、時間を行ったり来たりしているようなのも印象的。
時間という概念すらふわっとしていきますと、さらに観ている私たちと時の距離を感じなくなると思います。

一応はジェイミーの教育という事ながら、やはり主役はドロシア、アビーそしてジュリー3人の女性。
世界恐慌世代、パンクロックの到来やカウンターカルチャー直撃世代と、そんなものが当たり前でさてここからどうするかという世代。
彼女たちみんな素敵すぎる。
赤髪が最高に綺麗なグレタ・ガーウィグも、クールそうで一番迷ってるエル・ファニングも素晴らしいですが、やはりこれは母へのラブレター。
アネット・ベニングが間違いなく一番のスターですね。名演でしょう。彼女には本当に、恐慌時代に幼少期を生き、結婚から出産そして離婚まで経験した女性の厚みを感じます。
そしておそらくこの作品は、女性を軸においていてなおかつ女性の視点を突きつめ、女性映画としても最高峰なのではないかと感じます。
出てくる男はフェミニズムに目覚めていくジェイミーと、どちらかと言えばマッチョ系でセクシーなのに、繊細でちょい乙女なウィリアム。
ウィリアムの優しさを感じたのは、アビーとのラブシーン。まあ別に愛があったわけではなく、アビーは子宮頸がんを患うアビーではなく、誰か別の女性になりたかっただけ(だから変なロールプレイをしたのかと)ですが、ウィリアムはアビーその人を大切にしようとしていましたから。あんな男はそうはいない。
もちろん、「しっかりクリトリスを刺激して愛してあげなきゃ」という15歳少年もいないw
こうした人物に対する目線は、監督の個人的さが見えつつも、カメラのズームアップとアウトの絶妙さが、文字通り距離感を変えてくれているので、しつこくなりすぎずかつ他人ごとにもならない。巧いなぁ。

始まってすぐに流れる音楽のTalking Headsによる”Don’t Worry About The Government”がすごく象徴的かも。あれって最高に居心地のいいお家に、愛する人たちが集まっているって歌詞ですけど、この作品も、ジェイミーは輝く人たちに囲まれていますからね。
パンクロックの到来で、何かが変わり始めた時。この時をそれぞれの背景を持って生きて、それに直面した人たち。
色々と抱え込んで、世界と向き合いながら、それをジェイミーに吐き出して反射する。
おかしな女性ばかりで、ジェイミーはぐいぐいと引っ張られるままに成長しすぎてしまいますが、それでも非常にかけがえのない体験でしょう。
彼はこの夏に、ついに母を母ではなく一人の女性として観る瞬間を得たのです。
それは自立していて、男と付き合っていないからというだけでレズビアン扱いされることにあきれたり、ボガートのようになりたいという女性。
ドロシアがなんとも魅力的ですよ。冒険を忘れずに、高く高く飛んでいく。”As Time Goes By”と言うとおり、時は流れていきますが、ドロシアは常に世界に直面し自由に自分を持って生きていくから美しい。
直接でなくても、ドロシアはパンクロックをウィリアムと試してみて、そしてぎこちなくもジェイミーはクラシックな音楽にのせて母と踊ります。
この親子の歩み寄りも、周囲のみんなのおかしさもすごく好きな作品。コマ抜きしてブラーのかかる青春。
20世紀の女性たち。タイトルの通りに21世紀を前にドロシアはいなくなってしまうのですけども、余計に光るかな。かといってこの映画はノスタルジーに浸る者でもなく、カーター大統領の演説を交え、実は今に向けて語り掛けるものでした。
時間を越えつつ過去であり今であり、個人的でありつつ普遍的。
そしてなによりも輝く女性を彼女たちの視点からリアルに、その時で切り取った傑作ではないでしょうか。おススメの一本です。
ちょっと長くなったかな。こんなところで感想は終わりです。それでは、また~



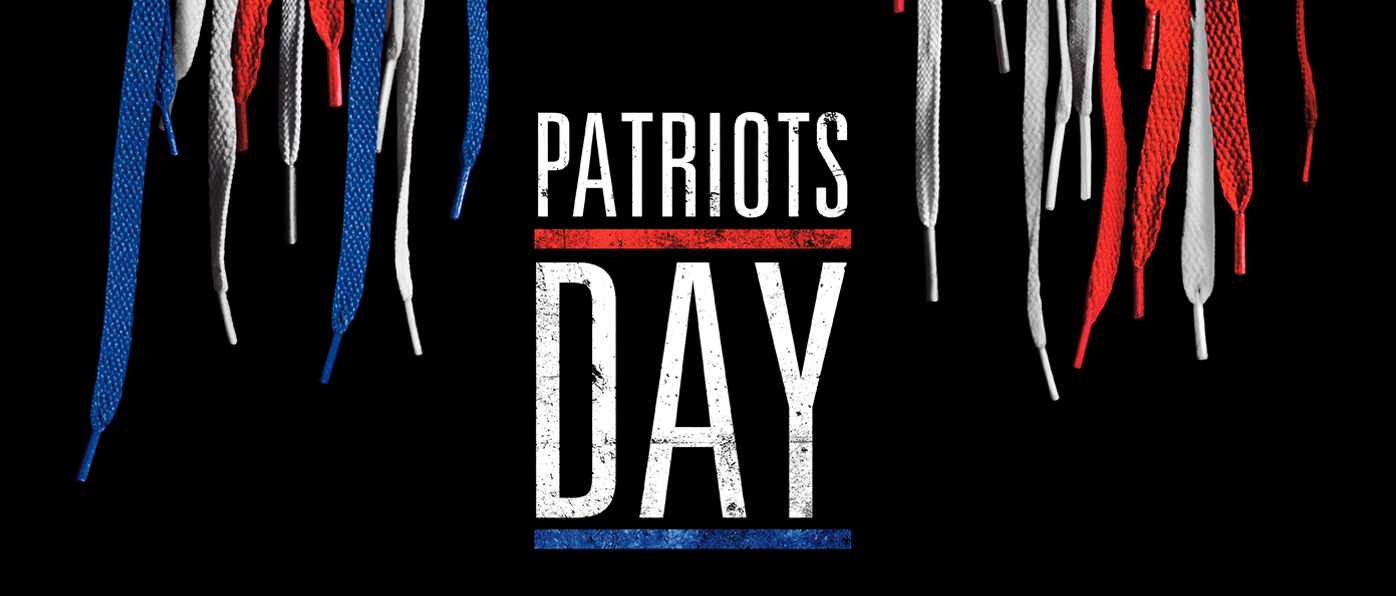
コメント